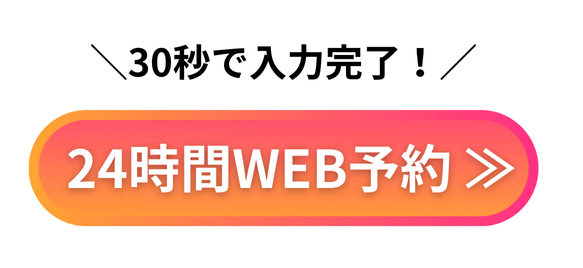「歯の神経を抜いたのに、まだ痛い…これって普通?」
そう不安に感じる方も多いでしょう。
通常、歯の神経を抜いた後の痛みは3〜7日程度でやわらぎます。ただし、症状の進み方や痛み方には個人差があり、中には長く続く場合もあります。
歯の神経を抜く治療(根管治療)とは、虫歯や炎症が進行して神経を残せない場合に行う治療です。本記事では便宜上「根管治療」という言葉で統一します。
この記事では、歯の神経を抜いた後の痛みが続く期間の目安、長引く原因や注意すべき症状、さらに自宅でできる痛みの緩和法について解説します。
目次
歯の神経を抜く治療後の痛みは何日続く?経過と注意点

根管治療後は、痛みの経過を知っておくことで不安を減らせます。ここでは一般的な回復の流れと、注意が必要なケースを整理しました。
- 痛みが落ち着くまでの一般的な期間
- 治療直後〜数日間に痛みが強まる理由
- 7日以上続く場合に考えられるトラブルと受診の目安
痛みが落ち着くまでの一般的な期間
多くの場合、 治療から3〜7日で痛みがやわらぎ、1週間以内にはほぼ気にならなくなります。
治療直後は一時的に症状が強まることもありますが、日ごとに改善し、普段通りの生活に戻れるのが一般的です。
治療直後〜数日後のピーク時の特徴と原因
痛みのピークは治療当日から2〜3日間です。
器具による刺激や歯内部の炎症反応により、噛む動作や温度差で敏感に反応します。
この時期は腫れやズキズキとした痛みを伴うこともありますが、多くは市販の鎮痛薬でコントロール可能です。
また、治療当日〜翌日は、血流の増加で痛みや腫れが強まるため、長時間の入浴やサウナ、激しい運動は避けましょう。
回復過程と7日以上続く場合の注意点
4日目以降は、しみる感覚や噛んだときの痛みが減り、食事や会話もしやすくなります。
ほとんどの方は1週間以内に症状が落ち着きますが、7日を過ぎても痛みが強い場合は注意が必要です。
特に痛みが悪化している場合や、腫れ・発熱を伴うときは、感染の恐れがあるため早めに歯科医院を受診しましょう。
関連記事:親知らず抜歯後の痛みのピークは2〜3日目|抜歯後の痛みを抑える方法も解説
痛みが長引く2つの主な原因
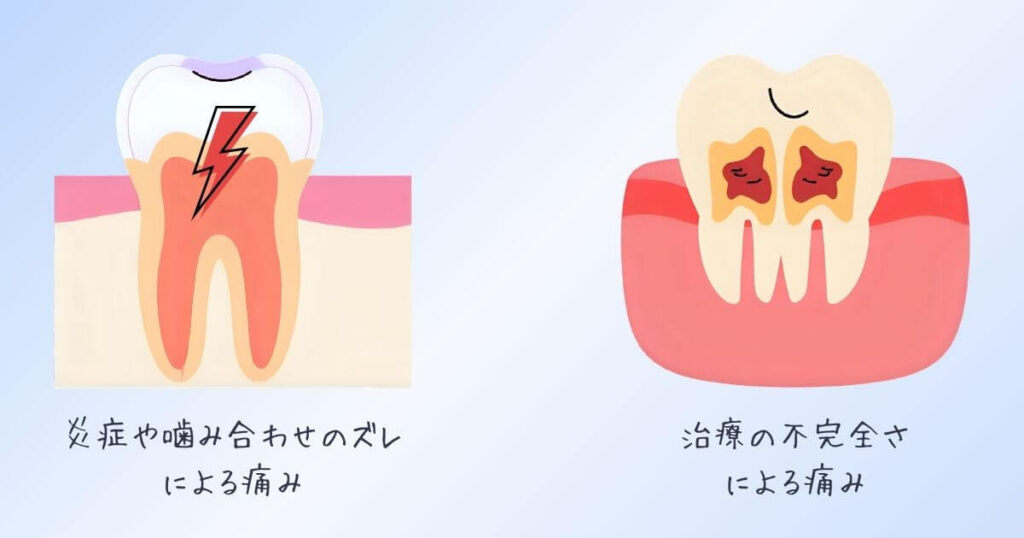
根管治療後に痛みが長引く場合、その原因として考えられるのは以下の2つです。それぞれの特徴と対処の必要性を解説します。
- 術後炎症や噛み合わせのズレで痛みが続くケース
- 治療が不完全な場合に起こる痛みとそのリスク
炎症や噛み合わせのズレによる痛み
治療は適切に行われていても、術後の組織反応として炎症が長引くことがあります。
また、詰め物や被せ物との噛み合わせが合っていないと、歯に余計な力がかかり、その刺激で炎症が悪化します。
噛んだ時だけ痛む、片側だけで噛んでしまうといった症状があれば、早めに調整を受けることが大切です。
治療の不完全さによる痛み
神経の一部や細菌が歯の内部に残っていると、根管内で持続的な感染や炎症が起こります。
この状態は時間が経っても自然に改善することはほとんどなく、多くの場合で再度の根管洗浄や消毒といった再治療が必要です。
放置すると炎症が歯茎や顎の骨にまで広がり、最終的には抜歯が避けられなくなるケースもあります。
早期の受診と適切な処置が、歯を守るためには欠かせません。
関連記事:かぶせた歯が噛むと痛い!いつまで続くの?痛いときの対処法も紹介
再受診が必要な3つのサイン

根管治療後に痛みや症状が悪化する場合、早めの受診が重要です。放置すると炎症や感染が広がり、抜歯のリスクも高まります。
ここでは、再受診を検討すべき3つのサインを解説します。
- 痛みが日に日に強くなっているケース
- 顔や歯茎の腫れが広がっているケース
- 発熱や全身のだるさを伴うケース
痛みが日に日に強くなっている
通常の回復過程では、治療後の痛みは時間の経過とともに軽くなるのが一般的です。
しかし、逆に痛みが増している場合は、根管内で炎症や感染が進行している可能性があります。
自然に改善することは少ないため、早めに歯科医院を受診しましょう。
顔や歯茎の腫れが悪化している
治療後の腫れが日に日に大きくなる、または歯茎から膿が出てくる場合は、炎症が歯や周囲の組織に広がっているサインです。
放置すると症状が悪化し、顎骨や全身への影響が出ることもあります。
発熱や全身のだるさを伴っている
37.5℃以上の発熱や全身の倦怠感がある場合は、細菌感染が全身に影響を及ぼしている可能性があります。
この状態を放置すると重篤化する恐れがあるため、すぐに医療機関で診察を受けてください。
関連記事:【医師監修】親知らずで発熱する原因|抜歯後の注意点も解説
根管治療後の回復を早める3つのセルフケア

根管治療後の過ごし方次第で、回復スピードや痛みの強さは大きく変わります。
ここでは、自宅で安全にできる痛み緩和と回復促進の3つの方法を解説します。
- 市販の鎮痛薬で適切に痛みをコントロールする方法
- 刺激を避ける食事や飲み方の工夫
- 冷却と安静による炎症の緩和
1. 市販薬で痛みをコントロール
痛みが強く、仕事や家事など日常生活に支障が出ている場合は、市販の鎮痛薬を適切に活用しましょう。
一般的にはイブプロフェンやアセトアミノフェンが使われますが、持病や他の薬との併用によっては使用できないことがあります。
服用時は必ず用法・用量を守り、不安がある場合は薬剤師や歯科医師に相談してください。
痛みが長引くときは自己判断せず、早めに受診することが大切です。
2. 刺激を避ける食事・飲み方
患部に刺激を与えないことが回復を早めるポイントです。
食事はやわらかく常温に近い食品(ヨーグルト、茶碗蒸し、煮込みうどんなど)を選びましょう。冷たすぎる飲み物や熱すぎるスープは、治療後の歯や歯茎に刺激を与えて痛みを悪化させます。
また、硬い食べ物や粘着性のある食べ物(キャラメル、ガム、硬いナッツなど)は詰め物や被せ物を傷める原因になるため、症状が落ち着くまでは控えるのが安心です。
3. 冷却と安静で炎症をやわらげる
腫れや炎症による痛みには、外側から頬を冷やすのが効果的です。
保冷剤や氷をタオルで包み、数分間あてては外すを繰り返すと血流が抑えられ、症状が軽減されます。
また、治療した側の歯で強く噛まない、長時間の会話を控えるなど、患部を安静に保つことも大切です。
就寝時は頭をやや高くして寝ると、血流が患部に集中するのを防ぎ、夜間の腫れや痛みの悪化を防げます。
関連記事:親知らず抜歯後の痛みに耐えられないときの対処法|おすすめの食事も紹介
神経を抜くことになった虫歯やトラブルを防ぐ3つの方法

根管治療は時間も費用もかかるうえに、治療した歯の寿命が短くなる傾向があります。多くの人が「もう二度と同じ治療は受けたくない」と感じることでしょう。
ここでは、根管治療の原因となるむし歯や歯のトラブルを防ぐ3つの予防法を解説します。
- むし歯を防ぐ食生活のポイント
- 定期検診で早期発見・予防する方法
- 毎日のホームケアで歯と歯茎を守るコツ
- 予防のメリットと避けたい習慣
1. むし歯を防ぐ食生活を意識する
むし歯は初期段階であれば削らずに経過観察できる場合もありますが、進行すると神経まで達し、根管治療や抜歯が必要になることがあります。
予防の基本は、糖分を控えた食生活と規則正しい歯磨きです。
特に間食の回数を減らすことで、口内が酸性の状態にある時間を短くし、むし歯菌が活動しにくい環境を整えられます。
厚生労働省の調査では、1日3回以上間食をする人は、間食をほとんどしない人に比べ、むし歯の発生率が約1.5倍に上ることが明らかになりました。
中でも就寝前の糖分摂取は危険度が高く、たとえ歯磨きをしても睡眠中は唾液が減るため、酸の影響が長時間続きます。甘い飲み物やお菓子はエナメル質を溶かしやすいため、時間帯にも注意が必要です。
2. 定期検診で早期発見・予防する
3〜6か月ごとの定期検診では、初期むし歯や歯のひび割れを早期に発見できます。
また、歯科医院ではフッ素塗布やシーラントといった予防処置も受けられるため、むし歯の再発防止や長期的な歯の健康維持に効果的です。
こうした定期的なメンテナンスは、自宅ケアでは防ぎきれないリスクを補う重要な役割を果たします。
3. 毎日のホームケアで歯と歯茎を守る
むし歯や歯周病を防ぐためには、毎日のセルフケアが欠かせません。
歯ブラシに加え、デンタルフロスや歯間ブラシを併用し、歯間や歯茎の境目に残るプラークをしっかり取り除きましょう。
これらの部位は特にむし歯や歯周病が発生しやすく、放置すると神経にまで影響することがあります。
また、フッ素配合の歯磨き粉を使うことで歯の再石灰化を促し、むし歯に強い歯質を維持できます。ブラッシング後は口を軽くすすぐ程度にして、フッ素が口内に残るようにしましょう。
特に就寝前は唾液が減り細菌が繁殖しやすくなるため、フロスとブラッシング、フッ素ケアを丁寧に行い、清潔な状態で眠ることが大切です。
予防を続けるメリットとNG習慣
予防習慣を続けることで、根管治療を避けられるだけでなく、口臭の防止や見た目の美しさの維持、噛む力の低下防止など、多くのメリットが得られます。
一方で、良かれと思って続けている習慣が、実は歯や歯茎に負担をかけていることもあります。
代表的な例が力を入れすぎた歯磨きです。過度なブラッシング圧は歯茎を傷つけ、知覚過敏の原因にもなります。
毛先のやわらかい歯ブラシを選び、ペンを持つような軽い力で磨くことが大切です。
また、無糖ガムは唾液分泌を促し口臭予防に役立ちますが、長時間噛み続けると噛み合わせや顎関節に負担がかかります。
特に顎関節症の症状がある方は注意が必要です。予防効果を得たい場合は、食後5〜10分程度を目安にしましょう。
関連記事:【現役歯科医師が監修】疲れて歯が痛いときの対処法8選|予防方法も解説
まとめ|痛みの経過を知り、再発予防まで見据えたケアを

歯の神経を抜いた後(根管治療後)の痛みは、多くの場合3〜7日で軽くなり、1週間以内に落ち着きます。治療直後はズキズキした痛みやしみる感覚が出やすいものの、日を追うごとに軽くなるのが一般的です。
ただし、7日以上経っても痛みが続く、悪化する、腫れや発熱を伴う場合は、炎症や感染の可能性があります。こうした症状が出たら、自己判断せず早めに受診しましょう。
回復を早めるためには、鎮痛薬の適切な使用、刺激を避けた食事、患部の冷却や安静などのセルフケアが有効です。
さらに、そもそも根管治療が必要になる事態を防ぐには、糖分を控えた食生活、定期検診、フロスや歯間ブラシを使った丁寧なホームケアが欠かせません。こうした予防習慣は再治療のリスクを減らし、健康な歯を長く保つ土台になります。
痛みの経過と適切な対処、そして日々の予防ケアを組み合わせることが、将来も健康な歯を保つための確かな方法です。
愛知県半田市で歯医者をお探しなら「歯科ハミール本院」
名鉄「住吉町駅」より徒歩1分の歯医者
当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。
この記事を監修した人

歯科ハミール本院 院長 赤崎 絢
所属学会
略歴