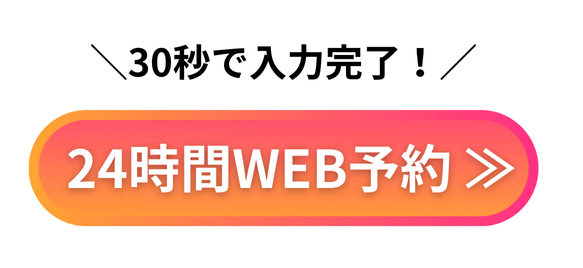親知らずを抜いたのに「根っこが残っている」と言われ、不安に感じたことはありませんか。実は、こうしたケースは決して珍しくありません。根が残っていたとしても、症状が出ずに経過することもあれば、炎症や痛みを引き起こす原因となる場合もあります。
この記事では、親知らずの根が残ったままになる主な原因や放置によるリスク、さらに治療が必要なケースとその流れについてわかりやすく解説します。
正しい知識を持ち、冷静に判断できるようにしましょう。
目次
親知らずを抜いたのに根っこが残ったままになる3つの原因

親知らずの抜歯では、歯や骨の状態によって根が残ることがあり、不安に感じる方も少なくありません。理由を知っておけば、必要以上に心配せずにすむでしょう。
代表的な原因は次の3つです。
- 根っこが折れてしまうケース
- 骨と根っこが強くくっついているケース
- 神経を傷つけないためにあえて残すケース
根っこが折れてしまうケース
親知らずの根は複雑で細く、途中で曲がっていることも少なくありません。そのため抜歯の際に力が加わると、一部が折れて残ってしまうことがあります。
歯科医師は専用の器具を用いて慎重に取り除きますが、無理に除去すれば周囲の骨や歯ぐきを傷つける危険があります。そのため、症状がなければあえて残す判断がとられることもあり、この場合は定期的な経過観察が重要です。
特に高齢の方では歯や顎の骨がもろくなり折れるリスクが高まるため、根を残すケースも少なくありません。
骨と根っこが強くくっついているケース
親知らずが長期間埋まったままでいると、歯の根が顎の骨と癒着してしまうことがあります。こうした癒着は特に高齢になるほど起こりやすく、抜歯を難しくする要因のひとつです。
無理にすべてを取り除こうとすると骨を大きく削る必要があり、術後の負担も大きくなるでしょう。
そのため、炎症や感染がなければ一部の根を残して経過観察とする対応がとられます。癒着の有無はCTやレントゲンで確認でき、治療方針を決めるうえで重要な判断材料となります。
神経を傷つけないためにあえて残すケース
下顎の親知らずは、太い神経(下歯槽神経)のすぐ近くに生えていることがあります。この場合、根を完全に取り除こうとすると神経を傷つけ、下唇や顎のしびれ、感覚麻痺などの後遺症につながる恐れがあります。
そのため、安全を優先し、根の一部をあえて残すこともあるでしょう。定期的にCTやレントゲンで経過を確認し、問題がなければ日常生活に支障なく過ごせます。
こうした神経を守るための判断は、後遺症を防ぐうえでとても重要です。
関連記事:【専門家が解説!】親知らずの安全な抜き方|抜歯後の注意点も解説
親知らずの根っこが残ったままでも大丈夫な3つのケース

親知らずの根が残っていると聞くと心配になりますが、必ずしも治療が必要になるわけではありません。状況によっては経過観察で問題ない場合もあります。代表的なのは次の3つです。
- 炎症や痛みが出ていない場合
- 骨と根っこが安定している場合
- 医師が安全性を優先して残すと判断した場合
炎症や痛みが出ていない場合
根が残っていても、痛みや腫れ、膿といった症状が出ていないなら、すぐに問題が起こる可能性は低いでしょう。レントゲンで異常が見られず、口内の清掃状態が良好であれば、そのまま経過観察となります。
定期的に受診して、根の周囲に変化がないか確認してもらいましょう。症状がなければ普段どおりの生活を送ることができます。
骨と根っこが安定している場合
親知らずの根が骨にしっかり固定されており、炎症もなく周囲の歯や歯ぐきに影響を与えていない場合は、そのまま残しても大きな問題はありません。骨と強く結合していれば動いたりずれたりする心配がなく、日常生活でも違和感を感じにくいでしょう。
ただし、将来的に体調の変化や加齢によって問題が出ることもあるため、定期的に歯科検診を受けて確認を続けることが大切です。
医師が安全性を優先して残すと判断した場合
神経や血管に近い位置にある親知らずは、前述のように無理に取り除くと後遺症のリスクが高まるため、歯科医師が残す判断をすることがあります。
親知らずを「残す」と聞くと不安に感じるかもしれませんが、安全性を重視した結果であり、定期的に状態を確認していれば心配しすぎる必要はありません。
親知らずの根っこが残ったまま放置すると起こる3つのリスク

前述のように、炎症や異常がなければ経過観察で問題ないケースもあります。しかし条件によっては、根が残ったまま放置することで将来的に大きなトラブルへ発展することもあるため、注意が必要です。
- 腫れや膿などの炎症が起こるリスク
- 隣の歯に悪影響が出るリスク
- 口臭や骨のダメージにつながるリスク
腫れや膿などの炎症が起こるリスク
根が残っている部分は細菌が入り込みやすく、炎症が起こりやすい環境です。感染すると歯ぐきの腫れや強い痛み、膿の発生につながり、さらに炎症を繰り返すと周囲の歯肉炎や顎の骨にまで影響が及ぶ場合があります。
感染が広がれば日常生活に支障をきたし、治療も難しくなるため、早めの対応が欠かせません。
隣の歯に悪影響が出るリスク
親知らずの根が残ったままの状態は、隣の歯に悪影響を及ぼす可能性があります。特に根の近くで細菌が繁殖すると、隣の歯の虫歯や歯周病の原因となりかねません。健康な歯まで巻き込まれると治療範囲が広がり、歯の寿命を縮めてしまうこともあります。
さらに、隣の歯の噛み合わせが乱れたり、歯列全体に悪影響が及ぶケースもあるため、放置は避け、定期的に受診することが大切です。
口臭や骨のダメージにつながるリスク
根の残骸がある部分は清掃が難しく、食べかすや細菌がたまりやすいため口臭の原因になります。さらに炎症が長引くと骨が溶ける「骨吸収」が進行することがあり、骨が失われると歯ぐきが下がってインプラントやブリッジなど将来的な治療にも支障が出る恐れがあります。
口臭の悩みや骨のダメージは見過ごされがちですが、生活の質に直結する重要なリスクといえるでしょう。
関連記事:親知らず抜歯にかかる実際の時間|親知らずを放置した時のリスクも解説
親知らずの根っこを取り除く必要がある場合と治療の流れ
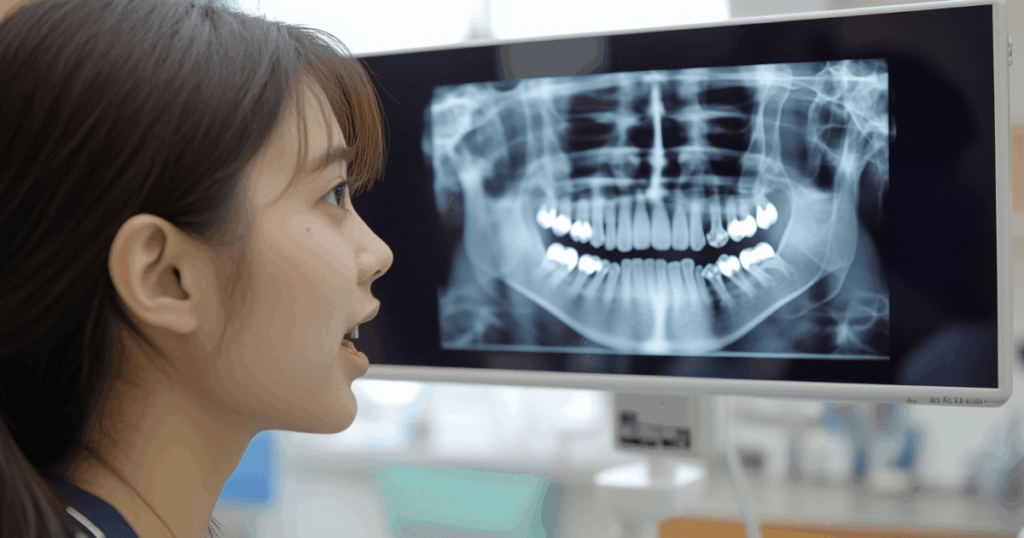
根が残っても問題ないケースは少なくありませんが、炎症や感染のリスクがある場合には取り除く治療が必要になります。あらかじめ流れを理解しておくと、不安なく治療を受けられるでしょう。
- CTやレントゲンでの診断の流れ
- 外科的に根っこを取り出す治療方法
- 術後の腫れや痛みに対するケア
CTやレントゲンでの診断の流れ
親知らずの根を取り除くかどうかは、まずCTやレントゲン検査で位置や形、神経や骨との関係を確認することから始まります。特に下顎の親知らずは神経に近い場合が多いため、画像診断でリスクを丁寧に把握することが欠かせません。
日本口腔外科学会でも、親知らずの抜歯にあたってはCTやレントゲンでの診断が重要とされています。的確な診断が行われれば、リスクを減らして安全に治療を受けることにつながるでしょう。
>>参照:日本口腔外科学会「親知らず」
外科的に根っこを取り出す治療方法
根を完全に取り除く必要があると判断された場合には、外科的な処置が行われます。歯ぐきを切開して根の部分を露出させ、骨を少し削って取り出すのが一般的です。状況によっては根を小さく分割し、少しずつ除去する方法がとられることもあります。
こうした処置は大学病院や口腔外科で行われることが多く、処置後は縫合して傷を保護します。手術時間は根の形や位置によって前後しますが、30分から1時間程度が目安です。
術後の腫れや痛みに対するケア
外科的処置の後は多くの場合、一時的な腫れや痛みが生じます。特に術後2〜3日は症状が強く出やすいため、正しいケアを続けることが大切です。処方された抗生物質や痛み止めを服用し、安静にしていれば症状は次第に落ち着いてきます。
冷却は術後48時間までが効果的で、それ以降は温めることで治りを早められます。食事は刺激の少ない柔らかいものを選び、喫煙や飲酒は控えましょう。こうしたセルフケアを守ることで、合併症のリスクを減らすことができます。
関連記事:親知らずが生えかけで痛いときの対処法|痛みを放置する7つの危険性も解説
親知らずの根っこが残りやすい人の特徴

ここで、根が残りやすい方の特徴を整理しておきましょう。あらかじめ知っておくことで、抜歯の前後に感じる不安をやわらげ、治療への心構えにもつながります。
- 根が細く曲がっている親知らず
- 骨に深く埋まっている親知らず
- 生え方や位置が特殊な親知らず
根が細く曲がっている親知らず
親知らずの根が細く、さらに途中で曲がっている場合は折れやすく、残りやすい特徴があります。特に下顎の親知らずに多く見られ、抜歯の難易度を高める要因のひとつです。
CTやレントゲンで根の形を事前に把握することで、無理のない方法を選び、安全性の高い治療につなげることができます。
骨に深く埋まっている親知らず
親知らずが骨の中に深く埋まっていると、根が骨と癒着して抜きにくくなることがあります。このような状態は「埋伏歯(まいふくし)」と呼ばれ、抜歯が難しい典型的なケースです。
無理にすべてを取り除こうとすると骨を大きく削らなければならず、手術後の腫れや痛みも強く出やすくなります。そのため、状況によっては根の一部を残して経過を観察することもあります。
CTやレントゲンで深さや角度を事前に確認し、その結果に応じて処置の方法や範囲が判断されます。
生え方や位置が特殊な親知らず
親知らずがまっすぐ生えず、斜めや横向きに生えている場合は、根が残りやすくなります。特に横向きの親知らずは隣の歯にぶつかることが多く、根全体を確認するのが困難です。また、奥に位置していると器具が届きにくく、完全に取り除くのが難しいケースも少なくありません。
こうした生え方は肉眼で判断できないことが多いため、CTやレントゲンで事前に状態を確認しておくことが大切です。
関連記事:【保存版】親知らずが埋まっているかどうかはレントゲンでわかるのか?
親知らずの根っこが残ったときのセルフケアと受診の目安

親知らずの根が残ったときのセルフケアや、歯科医院に行くべきタイミングは多くの方が気になるポイントです。正しい対処法と受診の目安を知っておけば、落ち着いて対応できるでしょう。
- 自宅でできる腫れや痛みへの対応
- どのような症状が出たら受診すべきか
- 定期的な検診で早めに確認する大切さ
自宅でできる腫れや痛みへの対応
親知らずの根が残って腫れや痛みを感じたときは、まず患部を清潔に保つことが重要です。うがい薬やぬるま湯でのやさしいうがいは細菌の繁殖を抑える効果がありますが、強くうがいすると傷口にできた血の塊(かさぶたのようなもの)が取れてしまうため控えましょう。
痛みが強い場合には市販の鎮痛薬で一時的にやわらげられますが、根本的な解決には歯科医院での診察が必要です。さらに、冷たいタオルで頬を軽く冷やすことで腫れを抑えられる場合もあります。
どのような症状が出たら受診すべきか
症状が軽度で落ち着いている場合は経過観察でも問題ないでしょう。しかし、強い痛みや歯ぐきの腫れ、膿が出る、口臭が強くなるなどの症状が見られたら、早めの受診をおすすめします。
これらは感染や炎症が進行しているサインで、放置すれば隣の歯や骨に悪影響が及ぶ可能性があります。
また、発熱を伴う場合や顔の腫れが広がる場合は緊急性が高いため、すぐに歯科医院を受診しましょう。早期の対応こそが重症化を防ぐ最善の方法です。
定期的な検診で早めに確認する大切さ
症状がなくても、親知らずの根が残っている場合は定期的に歯科検診を受けておくことが大切です。CTやレントゲンで状態をチェックすることで、炎症や感染の兆候を早期に発見できます。特に半年から1年に一度の検診は、将来的なトラブルを防ぐうえで効果的です。
異常が見つかれば早期の治療で負担を最小限に抑えることができ、結果的に費用や治療時間の軽減にもつながります。安心して日常を過ごすためにも、定期的な検診を習慣にしておくとよいでしょう。
まとめ|親知らずの根っこが残ったときに安心して対応するために

親知らずを抜いた後に根が残ると、不安や疑問を抱くのは自然なことです。しかし、多くの場合は医師の判断のもとで安全を優先して残されているケースもあり、必ずしも危険な状態とは限りません。
一方で、放置することで炎症や隣の歯への悪影響が生じるリスクもあるため、油断は禁物です。大切なのは、症状の有無にかかわらず定期的に歯科医院でチェックを受け、変化があればすぐに相談することです。
清潔を保つセルフケアを心がけながら、痛みや腫れが続くときは早めに受診し、トラブルを未然に防ぎましょう。
不安を感じたときに正しい情報を得て適切な対応をとることが、安心して日常生活を送るための最も確実な方法です。
愛知県半田市で歯医者をお探しなら「歯科ハミール本院」
名鉄「住吉町駅」より徒歩1分の歯医者
当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。
この記事を監修した人

歯科ハミール本院 院長 赤崎 絢
所属学会
略歴