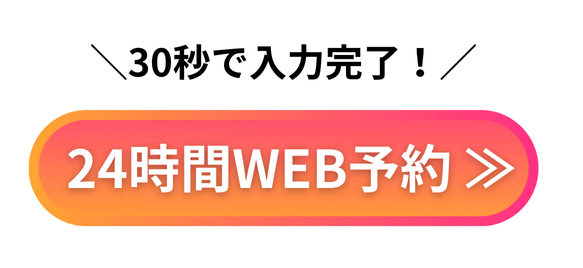頭痛と歯の痛みが同時に起こると、「なぜ?」と不安に思う方は少なくありません。
原因は虫歯や歯周病だけでなく、噛み合わせの不調や歯ぎしり、副鼻腔炎、さらには片頭痛が関係することもあります。
この記事では、頭痛と歯の痛みが同時に出るときの主な原因や受診の目安、自宅でできる応急処置・予防のポイントを、専門的な視点で分かりやすく解説します。
目次
頭痛と歯の痛みが同時に起こる3つの原因

歯の痛みと頭痛が重なるときは、複数の要因が関係していることがあります。歯や顎、鼻の奥などの異常が影響し合い、痛みが広がるケースも少なくありません。
主な原因は次の3つです。
- 虫歯や神経の炎症による痛み
- 副鼻腔炎(歯性上顎洞炎)の影響
- 噛み合わせや歯ぎしりによる筋肉の緊張
虫歯や神経の炎症による痛み
虫歯が神経まで進むと、ズキズキと脈打つような痛みが走ります。炎症がさらに広がると、痛みは歯だけにとどまらず、こめかみや頭にまで響きます。
夜になると痛みが強まり、眠れないほどつらく感じることもあるでしょう。冷たいものや甘いものがしみたりする場合は、炎症が神経の奥深くまで進んでいるサインです。
炎症が三叉神経にまで及ぶと、頭全体が締めつけられるような痛みへと変化します。
放置すると痛みが増して日常生活に支障をきたすおそれがあるため、早めに歯科医院で原因を確認することが大切です。
副鼻腔炎(歯性上顎洞炎)の影響
上の奥歯の根は、副鼻腔と非常に近い位置にあります。
そのため、虫歯や歯の根の炎症が広がると、副鼻腔まで波及して歯性上顎洞炎(しせいじょうがくどうえん)を起こすことがあります。
この病気では、頬や目の奥の痛み、頭の重さなどを伴うことが多く、単なる歯痛や頭痛との区別が難しいのが特徴です。
副鼻腔炎は決して珍しい病気ではなく、全国でおよそ100万〜200万人の患者がいるとされています。
多くの人が悩まされる身近な疾患のひとつともいえるため、歯痛と頭痛が同時に出るときは、この病気の可能性も念頭に置くことが大切です。
噛み合わせや歯ぎしりによる筋肉の緊張
噛み合わせのずれや、無意識の歯ぎしり・食いしばりがあると、顎からこめかみにかけての筋肉が強く緊張します。そのこりが神経を圧迫し、痛みが頭や歯へ広がることもあります。
特に歯ぎしりは睡眠中に起こりやすく、自分では気づきにくいのが特徴です。朝、顎のだるさやこめかみの重さを感じる場合は、筋肉の緊張が続いているサインといえるでしょう。
この状態を放っておくと、頭痛や顎の不調が慢性化し、日常生活にも影響を及ぼすおそれがあります。
歯のトラブルが頭痛を引き起こすケース
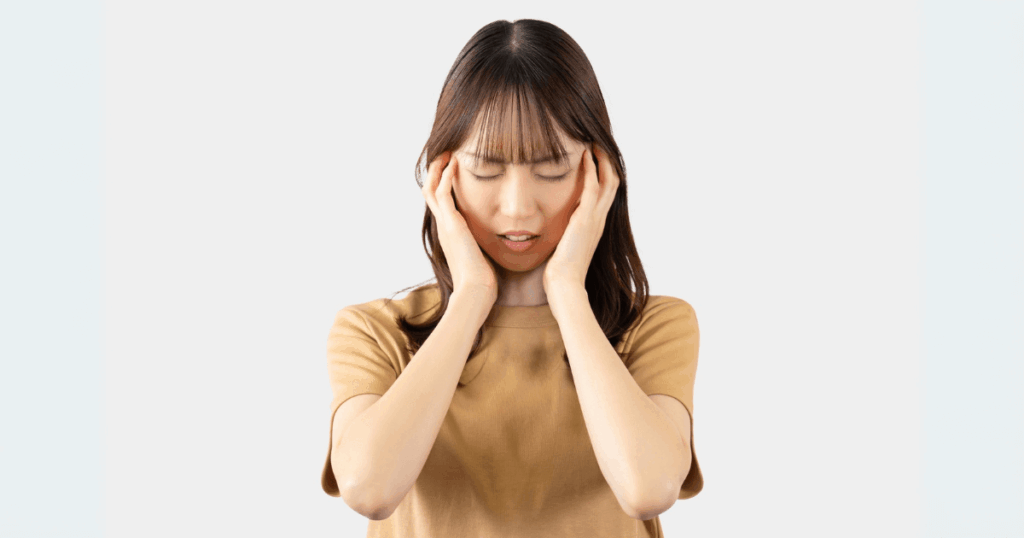
歯や歯茎の異常が、神経や筋肉を介して頭の痛みへと広がることがあります。歯と頭は密接に関係しており、炎症や圧力の影響が神経を伝わって、別の場所に痛みを感じる場合もあるでしょう。
ここでは、そうした中でも特によく見られる2つのパターンを取り上げます。
- 虫歯や歯周病による関連痛
- 噛み合わせのずれと顎関節の負担
虫歯や歯周病による関連痛
虫歯や歯周病が進行すると、歯の神経や歯茎だけでなく、顔や頭にまで痛みが広がることがあります。
これは「関連痛」と呼ばれ、実際には歯が原因で起きているにもかかわらず、頭痛のように感じられるのが特徴です。
なかでも歯周病は日本人の成人に多い身近な疾患で、厚生労働省の調査では、約半数の人に4mm以上の歯周ポケットがみられると報告されています。
炎症や膿が神経を刺激すると、痛みがこめかみや頭へと伝わり、慢性的な頭痛につながることもあるため注意が必要です。
歯や歯茎の違和感が続くときは、我慢せず早めに歯科医院を受診しましょう。
噛み合わせのずれと顎関節の負担
歯並びや噛み合わせが悪いと、噛むたびに顎関節やその周囲の筋肉へ不均等な力がかかり、これが痛みの原因です。
その状態が続くと筋肉がこり固まり、こめかみや後頭部に痛みを感じるようになるでしょう。
顎関節症は20〜40代の女性に多く見られる病気です。
「少しのずれだから」と放置すると、頭痛や首のこり、肩の重だるさへとつながるおそれがあるため、早めに歯科医院へ相談することが大切です。
頭痛が原因で歯が痛くなるケース

頭痛が原因で歯が痛くなることもあります。神経が過敏になったり血流が変化したりすると、歯そのものに異常がなくても痛みを感じることがあるのです。
こうした痛みは、どこが本当の原因なのか見分けがつきにくいのが特徴です。具体的には、次の2つの原因が関係していることがあります。
- 片頭痛による神経の刺激
- 緊張型頭痛と歯への影響
片頭痛による神経の刺激
脳の血管や神経の働きが一時的に乱れることで起こるのが、片頭痛です。このとき、顔や歯に分布する三叉神経に刺激が伝わると、歯の痛みとして感じられることがあります。
国内の調査では、15歳以上の日本人の約8.4%、およそ840万人が片頭痛に悩まされており、特に女性に多いとされています。
もし歯に異常が見つからないのに痛みが続く場合は、片頭痛による神経の刺激が関係しているかもしれません。
緊張型頭痛と歯への影響
長時間のデスクワークやストレスによって首や肩の筋肉がこると、緊張型頭痛を起こすことがあります。
この頭痛が続くと、緊張が顔や顎にまで広がり、歯の痛みとして感じられることもあります。
特に「夕方になると頭が重く、歯までじんじん痛む」という場合は、筋肉のこりが関係している可能性が高いでしょう。
同じ姿勢が続いたり、日常的にストレスを感じている方は、意識的に体をほぐすことが大切です。
頭痛・歯痛・目の痛みが同時に出るときに考えられること
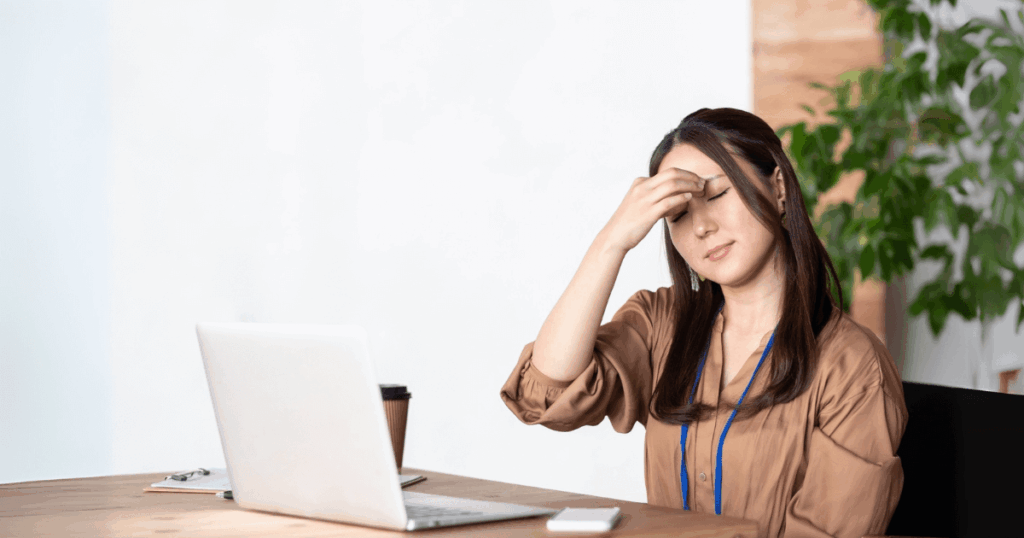
頭や歯に加えて目の奥まで痛むと、不安が強くなります。こうした症状が同時に起こる場合、複数の疾患が関係していることが少なくありません。
どのような要因が考えられるのか、順に見ていきましょう。
- 副鼻腔炎や眼精疲労との関係
- 片頭痛による目の奥の痛みと歯痛
- 危険な病気のサインを見逃さない
副鼻腔炎や眼精疲労との関係
副鼻腔炎は、鼻の奥にある空洞(副鼻腔)で炎症が起きる病気です。
上の奥歯の根に近い上顎洞で炎症が広がると、歯や頭だけでなく、目の奥にまで痛みを感じることがあります。
風邪のあとに「頭が重い」「歯が痛い」「目の奥がズキズキする」といった症状が出る場合は、副鼻腔炎を疑いましょう。
一方で、パソコンやスマートフォンの長時間使用による眼精疲労でも似たような痛みが起こります。
原因は異なりますが、どちらも筋肉や神経の緊張が関係しており、こまめに目を休めることが大切です。
片頭痛による目の奥の痛みと歯痛
片頭痛は、こめかみから目の奥にかけて強い痛みが出るのが特徴です。その影響で、顔や歯に分布する神経が刺激され、歯の痛みを伴うことがあります。
歯科医院で異常が見つからないのに、目の奥の痛みや歯のズキズキが続く場合は、片頭痛が関係している可能性があります。
痛みがくり返し起こるようであれば、頭痛外来などで相談してみるとよいでしょう。
危険な病気のサインを見逃さない
まれに、頭痛・歯痛・目の痛みが同時に現れる場合は、脳や神経の病気が関係していることがあります。
急に強い頭痛が起きたり、視界がぼやけたり、顔にしびれを感じたりする場合は、脳血管障害などの可能性も考えられます。
こうした痛みは日常的な頭痛との区別が難しいため、普段と異なる強い痛みや急に悪化した痛みを感じたときは、迷わず早めに医療機関を受診しましょう。
関連記事:【保存版】副鼻腔炎で歯が痛いときの対処法10選|歯が痛むときの特徴も解説
受診の目安と放置したときのリスク
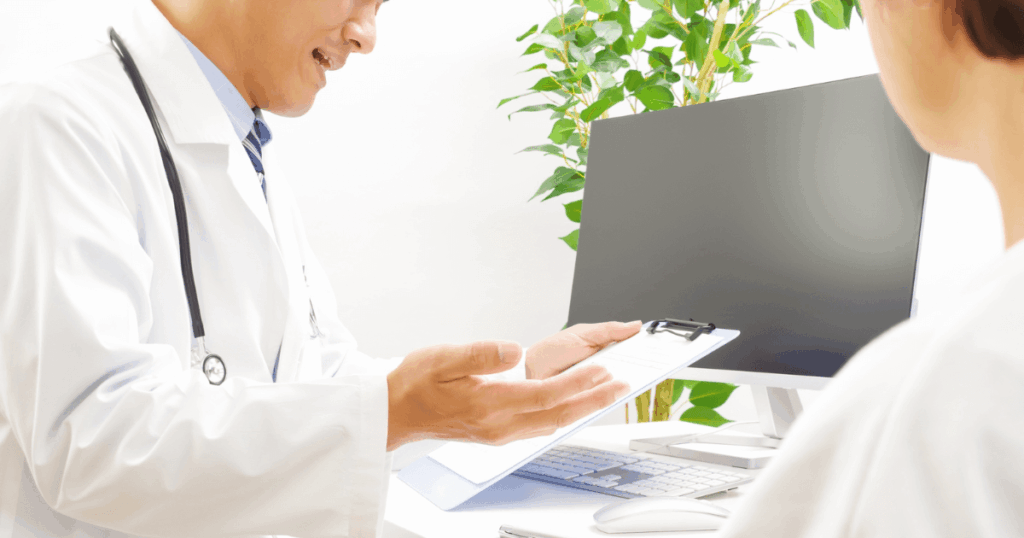
頭痛と歯痛が長く続くと、どのタイミングで病院へ行けばよいのか迷う方も多いでしょう。受診の判断基準を知っておくと、症状が悪化する前に落ち着いて行動できます。
ここでは、覚えておきたい2つのポイントを紹介します。
- 受診を急ぐべき症状のチェックリスト
- 放置で悪化する炎症や合併症
受診を急ぐべき症状のチェックリスト
次のような症状がある場合は、できるだけ早めに歯科医院や医療機関を受診しましょう。
- 歯の痛みが数日経っても治まらない
- 顔や頬の腫れ、発熱を伴う
- 目の奥やこめかみまで強い痛みが広がる
- 片側にだけ頭痛と歯痛が集中している
- 急に痛みが強まった
これらの症状は、虫歯の炎症や副鼻腔炎の悪化、または神経や血管の異常が関係していることもあります。
少しでも違和感が続くときは、放っておかず早めに歯科医院へ相談することが大切です。
放置で悪化する炎症や合併症
歯の痛みや頭痛を「そのうち治るだろう」と放っておくと、症状が広がって思わぬ合併症を引き起こすことがあります。
虫歯や歯周病が進行すれば、歯の根の感染が副鼻腔に及び、慢性副鼻腔炎へと発展するおそれもあります。
一方で、噛み合わせのずれや筋肉のこりを放置すると、顎関節や肩の痛み、さらには慢性的な頭痛につながることも少なくありません。
痛みを感じた時点で受診すれば、治療も軽く済み、重症化を防げるでしょう。
関連記事:片方の頬が腫れて押すと痛いときは何科へ?3つの判断基準
自宅でできる応急処置とセルフケア

忙しくてすぐに受診できないときでも、痛みをやわらげる工夫はできます。身近なもので行える応急ケアを知っておくと、症状の悪化を防ぎ、再発予防にもつながります。
- 痛みを和らげる方法(冷やす・温める)
- 姿勢や生活習慣の改善で予防する
痛みを和らげる方法(冷やす・温める)
歯や顎のまわりが腫れているときは、冷たいタオルや保冷剤をハンカチで包み、頬に当てて冷やしましょう。炎症がやわらぎ、痛みが落ち着きやすくなります。
一方で、筋肉のこりや緊張が原因の場合は、蒸しタオルで首やこめかみを温めるのが効果的です。血流が良くなり、頭痛や歯の痛みがやわらぐことがあります。
ただし、「冷やす」「温める」の判断は症状によって異なります。
短時間で改善が見られない、または痛みが強まる場合は、無理をせず早めに医療機関へ相談しましょう。
姿勢や生活習慣の改善で予防する
デスクワークで猫背の姿勢が続くと、首や肩の筋肉に負担がかかり、緊張型頭痛や歯の違和感を招きやすくなります。
背筋を伸ばし、こまめに休憩やストレッチを取り入れるだけでも、予防効果が高まります。
また、睡眠中の歯ぎしりや日中の食いしばりには、マウスピースの使用やリラックス習慣が有効です。
就寝前に深呼吸や軽いストレッチを取り入れることで、無意識の緊張をほぐせます。
さらに、生活リズムを整え、十分な睡眠とバランスの取れた食事を意識することも、歯や頭への負担を減らすために大切です。
どこに行けばいい?歯科・耳鼻科・内科の選び方

頭痛と歯の痛みが重なると、どの診療科を受診すればよいか迷うことがあります。それぞれの科が得意とする症状を知っておくと、早い段階で適切な治療につながります。
ここでは、受診の目安を整理して見ていきましょう。
- 歯科を受診すべきケース
- 耳鼻科で診てもらうべきケース
- 内科や頭痛外来に相談すべきケース
歯科を受診すべきケース
歯がしみる、噛むと痛む、歯茎が腫れているなどの症状があるときは、まず歯科医院を受診しましょう。虫歯や歯周病、歯の根の炎症が原因で頭痛が起きている場合があります。
特に上の奥歯に強い痛みを感じるときは、副鼻腔まで炎症が広がっている可能性があるため、早めの受診が大切です。症状の悪化を防ぎ、治療も短期間で済みやすくなります。
歯科医院ではレントゲンやCTで歯や顎の状態を詳しく確認できるため、痛みの原因が歯にあるかどうかを正確に見極められます。
耳鼻科で診てもらうべきケース
鼻づまりや膿のような鼻水、顔や目の奥の重い痛みを伴う場合は、耳鼻科での診察が適しています。
副鼻腔炎は、歯の痛みと頭痛を同時に引き起こす代表的な病気で、抗菌薬の投与や鼻の処置による治療が行われます。
歯科と耳鼻科では、症状が重なっていることも多く、見分けが難しいのが実際です。
歯科医院で異常が見つからなかった場合は、耳鼻科で副鼻腔の状態を確認してもらうとよいでしょう。
内科や頭痛外来に相談すべきケース
頭痛が主な症状で、吐き気や視覚の異常、光や音に過敏になるなどの症状を伴う場合は、内科や頭痛外来の受診が適しています。
片頭痛や緊張型頭痛が原因で、歯の痛みを感じるケースも少なくありません。
また、突然の激しい頭痛や、これまでにない強い痛みを感じるときは注意が必要です。
脳血管疾患など命に関わる病気の可能性があるため、救急外来を含めて早めの対応を検討しましょう。
予防のために日常でできること

頭痛と歯の痛みをくり返すと、集中力が落ち、生活の質にも影響します。しかし、日々のちょっとした工夫や習慣の見直しで、痛みを防ぐことは十分に可能です。
次の3つのポイントを意識して、健やかな毎日を保ちましょう。
- 定期健診と正しい歯みがき
- 歯ぎしりや食いしばり対策
- ストレスや生活習慣の見直し
定期健診と正しい歯みがき
歯の健康を守るためには、定期的な歯科健診が欠かせません。チェックを受けることで、虫歯や歯周病を初期の段階で発見でき、重症化を防げます。
また、毎日の歯みがきも大切です。
歯ブラシに加えてデンタルフロスや歯間ブラシを使えば、磨き残しを減らして清潔な口内環境を保ちやすくなります。
こうした習慣の積み重ねが、歯の痛みや頭痛を遠ざける大切な予防につながります。
歯ぎしりや食いしばり対策
睡眠中の歯ぎしりや、日中の無意識な食いしばりは、歯や顎に大きな負担をかける原因です。こうした状態が続くと、頭痛や歯の痛みへとつながることがあります。
就寝時はマウスピースを活用し、日中は上下の歯を軽く離す意識を持つようにしましょう。
さらに、硬いものを噛む習慣を控えたり、長時間同じ姿勢を取らないようにすることも、予防に効果的です。
ストレスや生活習慣の見直し
ストレスは、歯ぎしりや緊張型頭痛を悪化させる大きな原因です。
適度な運動や深呼吸、好きなことに打ち込む時間を持つなど、心と体をゆるめる工夫を取り入れましょう。
また、十分な睡眠と栄養バランスの整った食事を意識することも大切です。
生活リズムが整うことで、体の回復力や抵抗力が高まり、頭痛や歯の痛みが起こりにくくなります。
こうした日々の積み重ねが、歯や頭のトラブルを防ぐ基盤をつくります。
関連記事:歯の痛み ツボで和らげる方法|即効性と注意点から予防法まで解説
まとめ|頭痛と歯の痛みを感じたら早めの受診を

頭痛と歯の痛みが同時に起こるとき、その原因は虫歯や歯周病だけでなく、噛み合わせの不調や歯ぎしり、副鼻腔炎、そして片頭痛など多岐にわたります。
なかには目の痛みを伴う場合や、放置すると重い病気に発展することもあるため、自己判断は避けましょう。
まずは歯科医院を中心に受診し、必要に応じて耳鼻科や内科と連携していくのが適切です。
応急処置や生活習慣の見直しで一時的に和らぐことはあっても、根本的な改善には専門的な診断が欠かせません。
定期健診や日々のケアを続けることで、将来の頭痛や歯痛を防ぐことができます。
いつもと違う強い痛みや長引く症状を感じたときは、早めに医療機関へ相談し、健やかな毎日を取り戻しましょう。
愛知県半田市で歯医者をお探しなら「歯科ハミール本院」
名鉄「住吉町駅」より徒歩1分の歯医者
当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。
この記事を監修した人

歯科ハミール本院 院長 赤崎 絢
所属学会
略歴