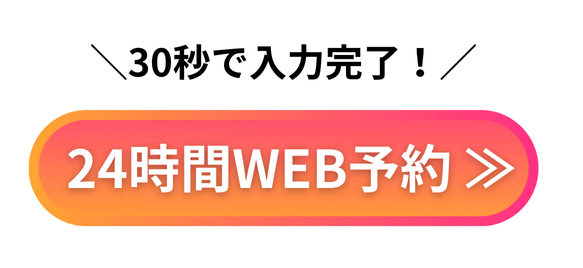「歯の神経を抜くことになったけど、どれくらい痛いのだろう……?」
「治療後も痛みは続くのかな……?」
虫歯の悪化で突然「神経を抜くしかない」と言われたら、多くの方が大きな不安を感じるでしょう。
しかし、根管治療(こんかんちりょう)とも呼ばれる神経を抜く処置は、局所麻酔によって処置中の痛みはほとんどありません。治療後の痛みも、過度に心配する必要はありません。
この記事では、治療中と治療後の痛みの違いや痛みを和らげる方法、さらに治療後に注意すべき点や費用の目安についても、わかりやすく解説します。
目次
歯の神経を抜く治療の痛みを理解する2つのポイント

過去に歯の治療で強い痛みを経験した方は「神経を抜く治療はもっと痛いのでは」と不安を感じることがあります。
ですが現在は麻酔や治療法が進歩し、治療中に強い痛みを感じることは少なくなっています。
ここでは、治療に関する痛みのイメージと実際の程度を整理してみましょう。
神経を抜くときの痛みのイメージ
神経を抜くと聞くと、多くの方が強い痛みを思い浮かべます。こうしたイメージは、麻酔技術が未発達だった時代の治療経験に基づいたものです。
しかし現在は局所麻酔の効果で治療中の痛みは大幅に軽減されます。古いイメージにとらわれず、正しい知識を持つことが大切です。
実際の治療で感じる痛みの程度
実際に神経を抜く治療を受けた方のなかには「虫歯を削ったときと変わらなかった」「ほとんど痛みを感じなかった」と話す方もいます。
局所麻酔が十分に作用するため、処置中の痛みはごくわずかであることが多く、むしろ治療前の痛みのほうが強かったと感じる方も少なくありません。
痛みの感じ方には個人差がありますが、多くの場合、治療前の強い痛みに比べると治療中の痛みは大幅に軽減されます。
関連記事:歯の治療中に麻酔が効きにくいのはなぜ?主な原因と対策
麻酔で痛みを防ぐために知っておきたい3つのこと

麻酔が効いている間は、治療中の痛みをほとんど感じません。ただし炎症が強い場合や体質によっては、麻酔の効果が弱まることがあります。
ここでは、局所麻酔の効果と安全性、まれに治療中に痛みを感じるケース、そして麻酔が切れた後の痛みの特徴について解説します。
局所麻酔の効果と安全性
局所麻酔は、神経を抜く治療で欠かせない処置のひとつです。一般的に使われるのはリドカインという薬剤で、短時間で効果が現れ、数時間持続するのが特徴です。
麻酔が作用している間は、歯を削ったり神経を取り除いたりする処置を行っても、強い痛みを感じることはほとんどありません。
「麻酔の注射が痛い」と感じる方もいますが、現在では表面麻酔を使って注射の刺激を抑え、極細の針や電動注射器を用いることで痛みを軽減しています。
さらに、適切に使用された局所麻酔は安全性が高く、副作用が起こることはまれです。アレルギーや体質に不安がある場合は、事前に歯科医に伝えておきましょう。
治療中に痛みを感じるケース
局所麻酔をしても、まれに痛みを感じます。炎症が強くて神経の周囲が腫れていると、麻酔の効果が弱まるためです。
痛みが出る場合でも、追加の麻酔や薬剤の変更によって抑えられるため、遠慮せず歯科医師に伝えましょう。
また、緊張や恐怖心によって痛みに敏感になる方もいます。できるだけ力を抜き、リラックスして治療を受けることが大切です。
麻酔が切れた後に出る痛みの特徴
治療が終わって麻酔が切れると、しびれが消えるのと同時に軽い痛みや違和感を覚えることがあります。これは処置による炎症が原因で、自然な反応です。
通常は1〜2日で落ち着き、処方薬や市販薬で対応できます。
関連記事:歯医者で抜歯の際に行う麻酔は何時間効くのか?|抜歯後の注意点についても解説
治療後の痛みの経過を知る2つの視点

神経を抜いた後の痛みがどのくらい続くのか、不安に感じる方もいるでしょう。数日以内に治まる場合がほとんどですが、まれに長引くこともあります。
ここでは数日以内に落ち着くケースと、長引く場合に考えられる原因に分けて解説します。
数日以内に落ち着く痛みのケース
神経を抜いた直後は、処置した歯の周囲に炎症が残っているため、噛んだときに違和感や軽い痛みを覚えます。通常は2〜3日で落ち着き、1週間もすれば気にならなくなるでしょう。
この段階での痛みは治療の影響による自然な反応であり、経過が順調に進んでいる証拠ともいえます。
必要に応じて市販の鎮痛薬を服用すれば、日常生活に支障をきたすほど強い痛みを感じることはありません。
長引く場合に考えられる原因
まれに、治療後も1週間以上強い痛みが続くことがあります。
主に、歯の奥に細菌が残っている、根の周囲に炎症が広がっている、詰め物が高く噛むと刺激になっているなどの原因が考えられます。
特に、治療後に強い腫れや膿が出る場合には、再治療や追加の処置が必要になることもあります。
痛みが長引いたり悪化したりするときは放置せず、早めに歯科医院に相談することが大切です。
関連記事:【現役歯科医師が監修】数ヶ月後に治療した歯が痛い場合の対処法
痛みを和らげるための2つの対処法

治療後の痛みは、市販の鎮痛薬や歯科医院での適切な対応によって和らげることができます。次に、薬の正しい使い方と、歯科医院に相談すべき症状について説明します。
市販薬の活用方法
神経を抜いた後の痛みは、多くの場合、市販の鎮痛薬で抑えられます。
一般的によく使われるのはイブプロフェンやアセトアミノフェンで、炎症をしずめながら痛みを和らげる効果があります。痛みが強くなってから飲むよりも、早めに服用したほうが効果的です。
ただし体質や持病によって使える薬は異なるため、普段から服用している薬がある方は、薬剤師や歯科医師に相談すると安心です。
正しく服用すれば、日常生活に支障をきたすほどの強い痛みが続くことは、ほとんどありません。
歯医者に相談すべき症状
市販薬を使っても痛みが治まらない、または時間とともに強くなっていく場合は注意が必要です。
特に腫れが強い場合や膿が出る場合、または発熱を伴う場合には、歯の奥に感染が残っている可能性があります。
放置すると炎症が広がり、治療が長引く原因となるため、早めに歯科医院に相談しましょう。
神経を抜いた歯のその後に関する3つの注意点

神経を抜いた歯は、その後の状態にも注意が必要です。歯が弱くなるリスクがあるほか、見た目や噛む力に影響が出ることもあります。そのため、定期的なケアを続けることが欠かせません。
ここでは、神経を抜いた歯に起こりやすい変化と、気をつけたいポイントを解説します。
歯が弱くなるリスク
神経を抜いた歯は血流や栄養の供給がなくなるため、時間の経過とともにもろくなります。
その結果、強い力がかかると歯が割れたり欠けたりする可能性が高まります。
こうしたトラブルを防ぐため、治療後には被せ物(クラウン)で補強するのが一般的です。
また、神経を抜いた歯は強い力に弱いため、氷やナッツなど硬い食べ物だけでなく、せんべいのような日常的なお菓子でも注意が必要です。
小さく割ってゆっくり噛むなど、歯に負担をかけない工夫をしましょう。
見た目や噛む力への影響
神経を抜いた歯は、時間の経過とともに変色し、周囲の歯より暗い色になります。
特に前歯では見た目に影響が出やすいため、ホワイトニングや被せ物で補修を行うケースも少なくありません。
また、神経を抜いた歯は感覚が鈍くなるため、噛む力の調整が難しくなります。その結果、無意識に強い力で噛んでしまい、噛み合わせが乱れることがあります。
周囲の歯や被せ物に負担がかかる場合もあるため、定期的に歯科を受診して経過を確認しましょう。
定期的なケアの必要性
神経を抜いた歯は、再感染のリスクが完全になくなるわけではありません。
根の奥に残った細菌の影響や、詰め物と歯の間にすき間ができることで炎症が再発することがあります。
そのため、治療後も定期的に歯科健診を受けて状態を確認してもらうことが大切です。
日々のブラッシングやデンタルフロスによるセルフケアを続ければ、治療した歯の再治療を防げます。
ブラッシングやデンタルフロスを習慣にすることが、治療した歯を長持ちさせる秘訣です。
神経を抜かずにすむ2つの治療法
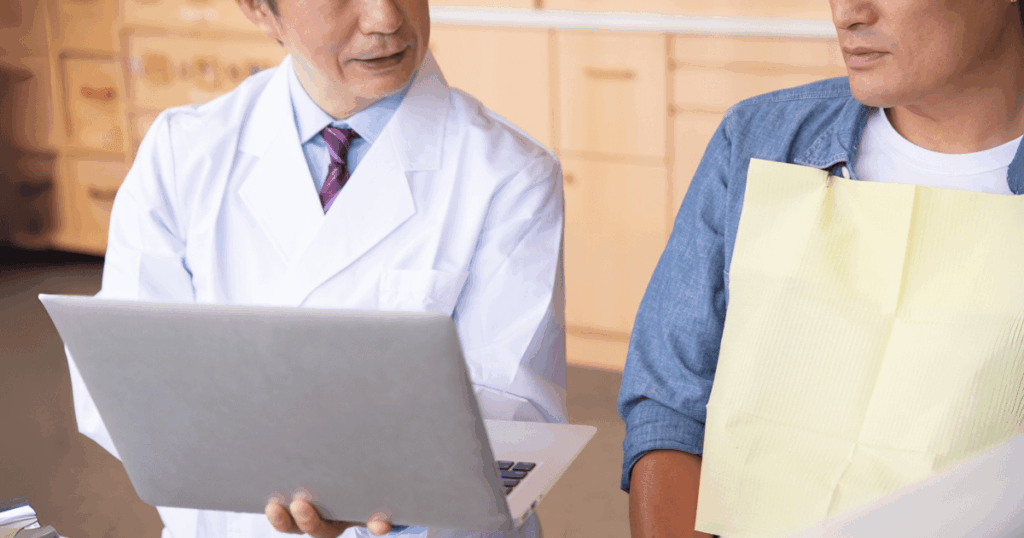
できるだけ神経を抜かずに歯を残したいと考える方は少なくありません。症状の程度によっては、神経を部分的に残す治療(プルポトミー)が選択できる場合もあります。
ここでは、神経を一部だけ取る治療と、それが難しい場合に行われる抜歯とを比較しながら解説します。
神経を一部だけ取る治療(プルポトミー)
虫歯の進行が浅くて神経の一部にだけ炎症がある場合は、神経の上部だけを取り除くプルポトミーという方法が選択されるケースもあります。
この処置によって歯の根元に残った健康な神経は温存され、歯の感覚や強さを保ちやすくなるのがメリットです。
特に若い方では、神経を残すことで歯の成長や強度の維持につながるため、有効な治療法です。ただし適用できるかどうかは症状によって異なるため、歯科医師の診断が欠かせません。
抜歯と比べた場合の違い
神経を抜く治療と抜歯は、性質の異なる選択肢です。
神経を抜いた歯は寿命が短くなるリスクはありますが、歯自体を残せるため噛む機能や見た目を保つことができます。
これに対して抜歯を行う場合は、ブリッジや入れ歯、インプラントなどの補綴治療(ほてつちりょう)が必要となり、費用や通院回数の負担が増えます。
いずれを選ぶにしても、治療方法については歯科医師と十分に相談することが大切です。
関連記事:親知らず抜歯後にやってはいけないこと7選|抜歯後におすすめの食事も紹介
費用や保険で知っておきたい3つのポイント

神経を抜くと治療費が高くなるのでは、と不安に思う方もいるでしょう。
多くの場合は保険診療が適用されるため、費用が大きく膨らむ心配はありません。ただし自由診療を選んだ場合や、再治療が必要になった場合には費用が高くなることがあります。
保険診療での費用の目安や、知っておきたい費用のポイントについて解説します。
保険診療でかかる費用の目安
神経を抜く治療には健康保険が適用されます。自己負担が3割の場合、前歯で3,000〜5,000円、奥歯で5,000〜8,000円が目安です。
ただし治療の回数や処置の難易度によって費用は変動します。
短期間で終わることもあれば、炎症や感染が強く複数回の通院が必要になることもあるため、あらかじめ歯科医師に費用の見通しを確認しておくと安心です。
自由診療や再治療にかかる費用
保険診療では対応できない特殊な器具や薬剤を使う場合には自費治療となり、費用が高くなります。
自由診療で行う神経を抜く治療は、1本あたり数万円から10万円前後です。また、一度治療した歯が再び感染して再根管治療が必要になると、さらに費用がかかります。
自由診療は精密な処置や成功率の高さに加え、見た目の自然さや長持ちといったメリットもあるため、費用とのバランスを考えて選択することが大切です。
費用を抑えるために知っておきたいこと
まずは保険適用の範囲を知っておきましょう。保険診療で対応できれば、費用を減らせます
もし高額な治療になった場合には、医療費控除を利用できる可能性があります。条件を満たせば確定申告で一部が還付される制度です。
高額療養費制度や自治体の医療費助成が利用できる場合もあるため、一度調べてみるとよいでしょう。
関連記事:【保存版】親知らず抜歯の費用|抜歯費用を抑える方法や抜歯後の注意点も解説
まとめ|歯の神経を抜く痛さを理解して治療に臨もう

歯の神経を抜く治療と聞くと、多くの方が強い痛みを想像して不安を感じます。しかし実際には、局所麻酔の効果で治療中の痛みはほとんどなく、治療後の痛みも数日以内に落ち着く場合が大半です。
痛みを和らげる方法や治療後に注意すべきポイントを理解しておけば、必要以上に恐れることなく治療に臨めるでしょう。
神経を抜いた歯は弱くなりやすく、炎症再発の可能性もあるため、定期的なケアと歯科健診が欠かせません。費用面では保険診療や医療費控除を活用すれば、経済的な負担を抑えられます。
歯を守るためには、早めの受診と正しい知識が大切です。痛みや不安を放置せず、信頼できる歯科医師に相談しながら治療を進めていきましょう。
愛知県半田市で歯医者をお探しなら「歯科ハミール本院」
名鉄「住吉町駅」より徒歩1分の歯医者
当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。
この記事を監修した人

歯科ハミール本院 院長 赤崎 絢
所属学会
略歴