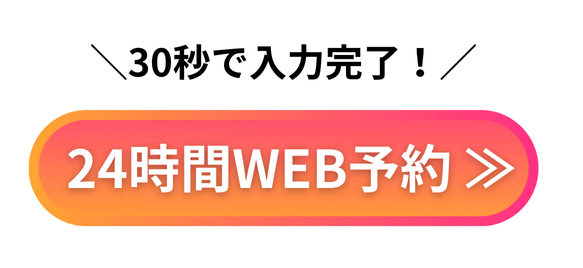「歯がズキズキ痛むのに虫歯が見当たらない」「歯医者で虫歯はないと言われたのに、奥がうずくように痛む」――そんな不安を抱えた経験はありませんか。
歯の神経の痛みは虫歯だけが原因ではありません。噛み合わせの不調やストレス、治療後の炎症など、さまざまな要因が関係しています。
この記事では、虫歯以外で歯の神経が痛む3つの原因と、早めに行うべき治療法・応急処置のポイントをわかりやすく解説します。
痛みの原因を正しく知ることで、不安を減らし、適切な対処につなげましょう。
目次
歯の神経が痛むのはなぜ?3つの主な原因を解説

歯の神経がズキズキと痛むとき、何が起きているのか分からず不安になる方も多いでしょう。多くの場合、その痛みは神経に炎症や圧迫が起きているサインです。
主な要因として、次の3つが挙げられます。
- 虫歯や根の炎症による神経トラブル
- 歯のヒビや詰め物の隙間からの細菌侵入
- 歯ぎしり・食いしばりによる神経圧迫
虫歯や根の炎症による神経のトラブル
歯の神経が痛む原因で多いのが、虫歯の進行による炎症です。虫歯がエナメル質や象牙質を超えて神経にまで達すると、細菌が入り込み、強い痛みを引き起こします。
炎症が神経の根まで及ぶと「歯髄炎」や「根尖性歯周炎」を発症し、ズキズキと脈打つような痛みが続くこともあります。
痛みが落ち着いたように感じても、内部では感染が広がっていることがあるため、注意が必要です。
早めに歯科医院を受診し、炎症の範囲に応じて適切な治療を受けることが大切です。
歯のヒビや詰め物の隙間から細菌が侵入するケース
虫歯がなくても、歯のヒビや詰め物の隙間から細菌が侵入し、神経の近くで炎症が起こることがあります。
硬いものを噛む習慣や歯ぎしりがあると、ヒビが入りやすく感染のリスクが高まります。
また、古い詰め物や被せ物の下で再感染が起きるケースも少なくありません。
詰め物の劣化や小さなヒビは見た目では分かりにくいため、定期検診でのチェックが欠かせません。
歯ぎしりや食いしばりによる神経への圧迫
就寝中の歯ぎしりや日中の食いしばりは、神経に負担をかける代表的な要因です。
強い力が歯に加わると、歯根の周囲にある血管や神経が圧迫され、炎症やうっ血が起こります。
その結果、虫歯がなくても「噛むと痛い」「歯が浮くように感じる」などの症状が現れます。
背景にはストレスや噛み合わせのずれが関係しているケースも多く、マウスピースの使用や生活習慣の見直しによって改善が期待できるでしょう。
虫歯ではないのに歯の神経が痛い3つの原因とは?
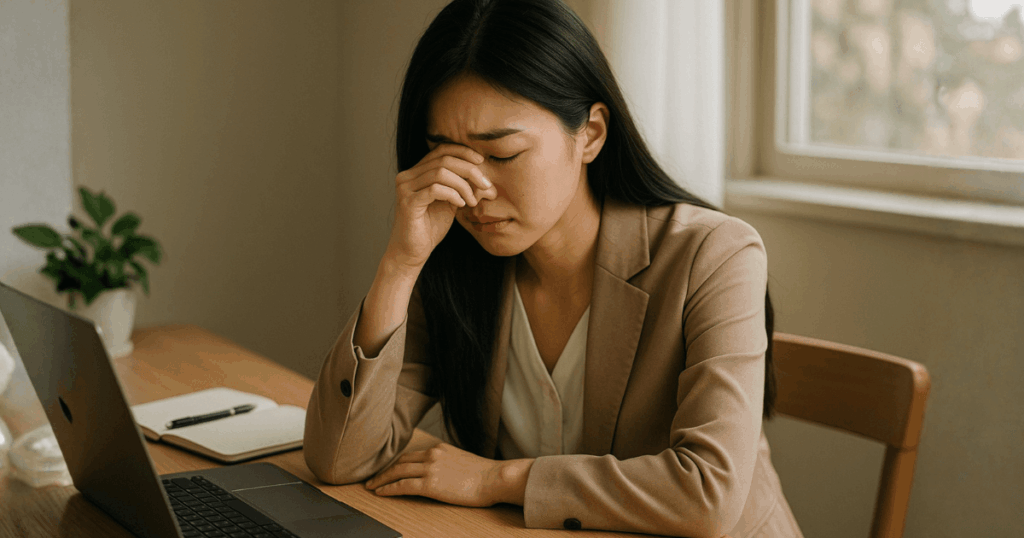
虫歯がないのに神経が痛む――そのようなときは、歯以外の要因が隠れていることもあります。
顎や筋肉、神経のトラブル、あるいはストレスや治療後の炎症など、原因は多岐にわたります。
それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。
- 顎や筋肉、神経が原因の痛み(非歯原性の痛み)
- ストレスや自律神経の乱れによる影響
- 治療後の炎症や再感染による痛み
顎や筋肉、神経が原因の痛み(非歯原性の痛み)
歯の神経が痛いように感じても、実際には顎や顔の筋肉、神経が原因になっている場合があります。代表的なのが「三叉神経痛」や「顎関節症」です。
これらは神経の過敏反応や関節への負担によって、歯が痛むような感覚を引き起こすのが特徴です。
虫歯治療をしても改善しない場合は、非歯原性の痛みの可能性があります。
神経内科や耳鼻科など、他の診療科での検査が必要になることもあるため、まずは歯科医院で相談してみましょう。
ストレスや自律神経の乱れが関係するケース
心身のストレスや自律神経の乱れによって、神経が過敏になり痛みを感じやすくなります。
仕事のプレッシャーや睡眠不足が続くと、歯ぎしりや食いしばりが起こりやすくなり、神経への圧迫が強まります。
慢性的な痛みが続く場合は、心理的な要因や自律神経の乱れが関係している可能性も否定できません。
意識的にリラックスする時間を持ち、生活リズムを整えることが回復につながります。
治療後に痛みが残るケース(治療後の炎症・根尖性歯周炎など)
虫歯治療や根管治療のあとに痛みが再発することもあります。これは歯根の先端に炎症が残る「根尖性歯周炎」によるもので、治療後の再感染が主な原因です。
数日~1週間は軽い痛みが出ることもありますが、噛んだときの痛みや腫れが続く場合は再治療が必要です。
見た目に異常がなくても、内部で炎症が広がるおそれがあるため、早めの再受診を検討しましょう。
関連記事:【9割が知らない】虫歯じゃないのに甘いもので歯が痛くなる原因|治療方法も紹介
放置するとどうなる?神経の痛みが続く3つのリスク

歯の神経の痛みを「そのうち治る」と放置してしまうと、炎症は静かに進行します。痛みが和らいだように見えても、内部では悪化している場合も少なくありません。
放置が招く主なリスクを、3つの視点から確認しておきましょう。
- 神経が死んで痛みが消える「手遅れ」の状態
- 顎の骨まで炎症が広がる危険性
- 治療が長引く・再発するリスク
神経が死んで痛みが消える「手遅れ」の状態
痛みがなくなったからといって、治ったと安心するのは避けましょう。
虫歯の進行によって一時的に痛みが消えることがありますが、これは炎症が進みすぎて神経が壊死した状態を意味します。
その間にも細菌は内部で活動を続け、歯の根や周囲の骨をじわじわと蝕んでいきます。
結果として歯がもろくなり、欠けたり割れたりして、最終的には抜歯が必要になる場合もあるでしょう。
顎の骨まで炎症が広がる危険性
歯の神経の炎症を放置すると、細菌が歯根の先端から顎の骨へと広がり、重い感染症である骨髄炎を引き起こすことがあります。
炎症が進行すると顎の骨が腫れ、顔全体がむくむほどになるケースも少なくありません。発熱や強い痛みを伴うこともあるでしょう。
この段階まで悪化すると、通常の歯科治療だけでは改善が難しく、外科的な処置が必要になる可能性が高まります。
治療が長引く・再発するリスク
神経の痛みを放置すると、感染が広がるだけでなく、治療期間も長期化します。
初期の段階であれば1〜2回の通院で済む虫歯も、炎症が進行すると根管治療や再治療が必要になり、数週間から数か月に及ぶこともあるでしょう。
さらに、一度治療を終えた歯でも、細菌が再び入り込めば痛みがぶり返すおそれがあります。
「我慢できるうちは大丈夫」と考えず、違和感を覚えた時点で受診することが、歯を守るための大切な行動です。
関連記事:歯の神経を抜く痛さを和らげるために、知っておきたい7つのこと
歯の神経が痛いときの3つの治療法と通院の流れ

神経の痛みを感じたとき、どんな治療を受けるのかを知っておくと安心です。症状の進み具合によって、治療法や通院回数は大きく変わります。
ここでは代表的な3つの治療法と流れを紹介します。
- 神経を残す治療(歯髄保存療法)
- 神経を取る治療(根管治療)
- 治療期間と通院回数の目安
神経を残す治療(歯髄保存療法)
炎症が軽度の場合は、できるだけ神経を残す「歯髄保存療法」が行われます。
虫歯の部分だけを丁寧に取り除き、抗菌薬や特殊な薬剤で神経を保護しながら自然治癒を促す方法です。
神経を残すことで歯の寿命を延ばし、将来的なもろさや再感染のリスクを減らす効果が期待できます。
ただし、炎症が深い場合は効果が限定的で、痛みや腫れが強いときには根管治療に移行することもあります。
できるだけ早めに受診することが、神経を残すための重要なポイントです。
神経を取る治療(根管治療)
虫歯や炎症が神経まで達している場合には、感染した神経を取り除く根管治療が行われます。
歯の内部を丁寧に清掃・消毒し、細菌が繁殖しないよう薬剤を詰めて密閉する治療です。
この処置は非常に繊細で、歯の中をミリ単位で扱う必要があるため、数回に分けて行われるのが一般的です。
治療後は被せ物で歯を保護し、細菌の再侵入を防ぎます。
治療期間と通院回数の目安
歯の神経治療にかかる期間は、症状の進行度や歯の部位によって異なります。
軽度の虫歯で神経を残せる場合は、1〜2回の通院で治療が完了することもあります。
一方、根管治療になると3〜5回ほど通うケースが多く、感染の範囲によってはさらに時間を要するでしょう。
途中で治療を中断すると、細菌が再び増殖して炎症が再発する原因となるため注意が必要です。
治療後は1〜2週間ほどで痛みが落ち着くのが一般的ですが、再発を防ぐためには定期的なチェックも欠かせません。
歯科医と相談しながら、自分の症状に合わせた治療計画を立てることが大切です。
痛みをやわらげる3つの応急処置とセルフケアの注意点

突然の痛みに襲われ、すぐに歯医者へ行けないこともあるでしょう。そのようなときは、正しい応急処置を知っておくことが心強い支えになります。
自宅でできる対処法と、避けるべき行動を整理しておきましょう。
- 市販薬や冷やす方法で痛みを一時的に和らげる
- NG行動(温める・飲酒・運動)に注意
- 夜中や休日に痛みが出たときの対応法
市販薬や冷やす方法で痛みを一時的に和らげる
歯の神経が痛むときは、市販の鎮痛薬を正しく使用することが効果的です。
イブプロフェンやアセトアミノフェンなどの成分には、炎症を抑えて痛みを軽減する作用があります。
さらに、痛みのある部分を冷たいタオルや保冷剤で軽く冷やすと血流が落ち着き、痛みが和らぐでしょう。
ただし、歯に直接氷を当てたり、長時間冷やし続けたりすると、かえって刺激になり逆効果となりかねません。
冷やすときは、短時間を目安に行うようにしましょう。
NG行動(温める・飲酒・運動)に注意
歯が痛むときは、体を温める行動を控えることが大切です。
熱いお風呂やサウナ、激しい運動、アルコールの摂取は血流を促進し、炎症を悪化させる原因になります。
さらに、患部を舌や指で触ったり、冷水を何度も口に含んだりする刺激も避けましょう。
痛みを感じたときは安静を心がけ、できるだけ刺激を与えないようにすることが、回復を早めるポイントです。
夜中や休日に痛みが出たときの対応法
夜間や休日など、すぐに歯科を受診できないときは、応急処置で痛みをやわらげながら過ごすことが大切です。
横になると血流が頭部に集まりやすく、痛みが強まることがあります。上半身を少し起こした姿勢で休むと、楽に感じられるでしょう。
強い痛みが続いたり、腫れを伴ったりする場合は、救急歯科や夜間診療を利用するのも有効です。
無理に我慢せず、翌朝には必ず歯科医院を受診して原因を確認しましょう。
関連記事:歯の神経 抜いた後 何日くらい痛いのかを解説|痛みの目安と対処法3選
再発や悪化を防ぐための3つの予防と生活習慣

治療が終わっても油断は禁物です。再び痛みが起こるのを防ぐには、日常のケアと生活習慣の積み重ねが欠かせません。
今日から意識したい3つの習慣を紹介します。
- 定期検診で早期発見・早期治療を心がける
- 正しいブラッシングとフロスの使い方を見直す
- 食生活や歯ぎしり対策で神経への負担を減らす
定期検診で早期発見・早期治療を心がける
歯の神経の痛みを防ぐうえで有効なのは、定期的に歯科検診を受けることです。
虫歯や詰め物の劣化、噛み合わせのずれなどは自覚しにくく、気づかないうちに進行していることがあります。
そのため、半年に1回を目安に検診を受けておくと、早期発見・早期治療につながります。
小さなトラブルの段階で処置すれば、神経まで炎症が及ぶのを防げるでしょう。
また、定期的な歯石除去やクリーニングも、再発予防に効果的です。
正しいブラッシングとフロスの使い方を見直す
歯みがきの癖や磨き残しは、虫歯や歯周病を引き起こす原因になります。
歯ブラシの毛先を歯面に軽く当て、小刻みに動かして1本ずつ丁寧に磨くことを意識しましょう。
力を入れすぎると歯茎を傷つけ、かえって知覚過敏を悪化させることがあります。
また、歯ブラシだけでは落としにくい歯と歯の間の汚れは、デンタルフロスや歯間ブラシを併用すると効果的です。
毎日のケアを少し丁寧に続けるだけでも、神経への炎症や再発のリスクを大きく減らすことができます。
食生活や歯ぎしり対策で神経への負担を減らす
食生活は、歯や神経の健康に深く関わっています。
甘いものや炭酸飲料を頻繁に摂取すると、口内が酸性に傾き、虫歯が進行しやすくなります。食後は早めに歯を磨くか、水で口をすすぐ習慣をつけることが大切です。
また、睡眠中の歯ぎしりや日中の食いしばりは、神経を圧迫し、痛みや炎症の原因となります。
歯科医院でマウスピースを作成し、歯への負担を軽減する工夫を取り入れると、予防効果が高まります。
関連記事:虫歯の初期に出る痛みを見逃さない6つのチェックポイント
まとめ|歯の神経の痛みは早めの受診で防げる

歯の神経の痛みは、虫歯の進行だけでなく、歯ぎしりやストレス、治療後の炎症など、さまざまな要因によって起こります。
痛みを放置すると、神経が壊死して歯を失うリスクが高まり、顎の骨にまで炎症が及ぶこともあるでしょう。
冷やしたり鎮痛薬を使ったりする応急処置は一時的な緩和にはなりますが、根本的な解決には早期の受診が不可欠です。
治療後も定期検診や日々のケアを続け、再発を防ぐ習慣を身につけましょう。
「少しおかしいな」と感じた段階で受診すれば、神経への負担を最小限に抑え、長期的な口腔健康の維持につながります。
愛知県半田市で歯医者をお探しなら「歯科ハミール本院」
名鉄「住吉町駅」より徒歩1分の歯医者
当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。
この記事を監修した人

歯科ハミール本院 院長 赤崎 絢
所属学会
略歴