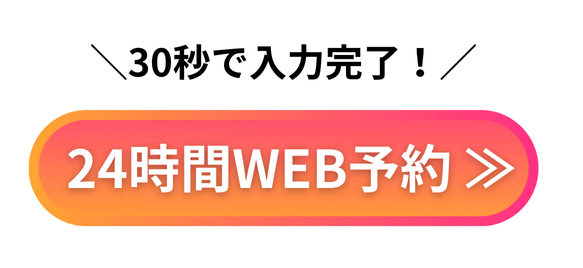「食べ物が挟まっただけ」と思っていたら、歯と歯の間がズキズキ痛む……そんな経験はありませんか。
この痛みは、単なる食べかすのつまりだけが原因とは限りません。
虫歯や歯ぐきの炎症、噛み合わせの不調など、複数の要因が重なって起こることもあります。
この記事では、歯と歯の間が痛む主な原因と、自宅でできるケア、そして歯科医院での治療が必要なサインについてわかりやすく解説します。
目次
歯と歯の間が痛い4つの原因とは?よくあるケースを紹介

食事中や歯みがきのときに、歯と歯の間がズキッと痛むと不安に感じるでしょう。
痛みの裏には、歯ぐきの炎症や虫歯が隠れていることがあります。ほかにも噛み合わせのずれが関係している場合もあり、原因は一つとは限りません。
ここでは、よく見られる4つの原因を取り上げ、それぞれの特徴を詳しく紹介します。
食べ物が挟まって炎症を起こしている場合
食後に歯と歯の間が痛む一般的な原因は、食べ物の残りや繊維質の食材が挟まることです。
特に肉や野菜の繊維、ポップコーンの皮などは歯ブラシでは取り除きにくく、残ったままだと細菌が繁殖して歯ぐきに炎症を起こします。
この炎症は歯間乳頭炎と呼ばれ、痛みや軽い出血を伴います。放置すると炎症が広がり、歯周病の初期段階に進むおそれがあるため注意が必要です。
虫歯が歯と歯の間にできている場合
歯と歯の間(隣接面)にできる虫歯は外から見えにくく、痛みを感じたときにはすでに進行していることが少なくありません。
初期のうちは冷たいものがしみる程度ですが、炎症が神経に近づくにつれてズキズキとした強い痛みに変わってきます。
隣接面の虫歯は自然には治らないため、削って詰める治療が必要です。
早期に発見できれば小さな詰め物で済みますが、放置すると神経を取る治療や、場合によっては抜歯が必要になることもあります。
歯ぐきの腫れ・歯周病による痛みの場合
歯と歯の間の歯ぐきが腫れて痛むときは、歯肉炎や歯周病の可能性が高いでしょう。
歯垢(プラーク)に含まれる細菌が歯ぐきに炎症を起こし、腫れや出血、痛みを引き起こします。
特に40代以降は加齢によって歯ぐきが下がり、歯の間が広がって汚れがたまりやすくなります。
歯周病が進行すると、歯を支える骨(歯槽骨)が溶け、歯がぐらつく原因になるため、早めのケアが欠かせません。
噛み合わせや歯のひび割れが原因の場合
強い食いしばりや歯ぎしりによって特定の歯に過度な力がかかると、歯に小さなひび(マイクロクラック)が入ることがあります。
ひびのすき間に細菌が入り込んで炎症を引き起こすと、噛むたびに痛みを感じるようになります。
また、被せ物や詰め物の高さが合っていない場合も、特定の歯に負担が集中して痛みを感じるでしょう。
放置するとひびが広がり、最終的に歯が割れてしまうおそれがあるため、歯科医院での噛み合わせ調整が欠かせません。
関連記事:虫歯の初期に出る痛みを見逃さない6つのチェックポイント
自宅でできる3つの応急処置とケア方法

歯と歯の間が痛むとき、自分で何とかしたいと感じる方も少なくありません。
ただし、誤ったケアは炎症を悪化させるおそれがあります。
ここでは、痛みをやわらげながら清潔な状態を保つための基本的なケア方法を紹介します。正しい手順を押さえて、落ち着いて対応しましょう。
歯間ブラシやデンタルフロスで汚れを取り除く方法
まずは、歯と歯の間に残った汚れをやさしく取り除きます。
歯間ブラシは無理に押し込まず、歯ぐきを傷つけない程度の力でゆっくり前後に動かしましょう。
デンタルフロスを使う場合は、歯の側面に沿わせて上下に動かし、汚れをなぞるように落とします。ギシギシと強くこすらず、滑らかに通すのがコツです。
出血がある場合は、歯ぐきに炎症が起きているサインと考えましょう。
毎日丁寧なケアを続ければ1週間ほどで症状は落ち着きますが、出血が長く続く場合は、歯科医院での診察をおすすめします。
痛みをやわらげる冷却と市販薬の使い方
強い痛みがあるときは、炎症を抑えることが重要です。
頬の外側から冷たいタオルや保冷剤をあて、10分ほど冷やすと血流が落ち着き、痛みがやわらぎます。ただし、長時間の冷却は逆効果となるため注意しましょう。
また、市販の鎮痛薬(ロキソニン・イブなど)を活用するのも一時的な対処として有効です。空腹時を避けて水で服用し、痛みがやわらいでいる間に歯科医院を予約しておくと安心です。
鎮痛薬はあくまで一時的な手段のため、根本的な治療にはなりません。痛みが消えたとしても安心せず、早めの受診を心がけましょう。
炎症を悪化させないための注意点
歯の痛みを感じると、つい強く磨いたり、指で触れて確かめたくなったりします。
しかし、過度な刺激は炎症を悪化させる原因となるため注意が必要です。歯ブラシは毛先が柔らかいものを選び、力を入れずに軽く動かします。
また、熱い飲み物や辛い食べ物、アルコールは血流を促進し、痛みを強めます。症状が落ち着くまでは控えましょう。
夜間の痛みが強いときは、枕を少し高くして眠ると血液が頭部に集まりにくくなり、痛みの緩和につながります。
こうした工夫で症状を抑えつつ、できるだけ早めに歯科医院を受診することが大切です。
痛みが続くときに考えられる3つの病気

数日経っても歯と歯の間の痛みが引かない場合は、虫歯以外の病気が関係しているかもしれません。
例えば神経の炎症や歯の根のひび割れ、副鼻腔炎などが考えられます。
痛みが長引くときに考えられる3つの主な病気について、症状の特徴と早めに受診すべきサインを解説します。
神経の炎症や根の先に膿がたまっている場合
冷たいものや熱いものがしみたり、噛んだときにズキズキと痛みが続いたりする場合に考えられるのは、歯の神経(歯髄)の炎症です。
この状態を放置すると神経が死に至り、根の先に膿がたまる根尖性歯周炎に進行するおそれがあります。
膿ができると強い噛み痛みや頬の腫れ、発熱を伴うことがあり、歯科医院では神経を除去する根管治療が行われます。
早期に治療すれば、歯を残せる可能性が高まるでしょう。
歯の根が割れている・ヒビが入っている場合
歯ぎしりや食いしばり、または硬い食べ物を噛んだ衝撃によって、歯の根や歯冠にヒビが入ることがあります。
進行すると噛むたびにズキッとした痛みを感じ、炎症が広がって歯ぐきも腫れてきます。
ヒビの位置や深さによっては抜歯が必要ですが、早期に発見できれば被せ物の調整や部分的な修復で対応できる可能性があります。
噛んだときだけ痛みが出る場合は、歯のひび割れを疑い、歯科医院での検査を受けましょう。
歯以外の病気(副鼻腔炎や神経痛など)の可能性
歯そのものに異常がなくても、周囲の組織や神経が原因で痛みを感じることがあります。
例えば、副鼻腔炎(蓄膿症)では、上の奥歯の根に近い上顎洞に炎症が広がり、歯の痛みのように感じられます。
また、顔面神経痛の一種である三叉神経痛は、突然電気が走るような鋭い痛みが特徴です。
歯に問題が見つからないのに強い痛みが続く場合は、耳鼻科や神経内科の受診も検討しましょう。
歯と歯の間の痛みが長く続く場合は、必ずしも歯だけの問題とは限りません。適切な医療機関で原因を確認することが重要です。
関連記事:片方の頬が腫れて押すと痛いときは何科へ?3つの判断基準
歯医者に行くべき3つのサインと受診の目安

痛みが続いても、「もう少し様子を見ても大丈夫かな……」と受診を先延ばしにする方は少なくありません。
しかし、歯と歯の間の痛みには、早めの治療が必要なケースがあり、放置すると悪化して治療の範囲や期間が大きくなる恐れもあります。
この章では、歯科医院を受診すべきサインと、症状の重さを見極めるためのポイントを解説します。
すぐに受診が必要な症状
次のような症状がある場合は、早急に歯科医院を受診しましょう。
- 痛みが強く、夜眠れないほど続く
- 頬や歯ぐきが腫れている
- 冷たいもの・熱いものの両方にしみる
- 噛むと強い痛みがある
- 発熱やリンパの腫れを伴う
これらの症状は、炎症の進行を示唆しています。放置すると膿がたまり、顔の腫れや高熱などへ発展するおそれがあります。
様子を見てもよい軽度の痛みとは
軽く痛む程度で、次のような症状の場合は、1〜2日ほど様子を見ても問題ないでしょう。
- 食べ物が挟まったあとに一時的に痛む
- フロスや歯間ブラシを使ったあとに軽くしみる
- 歯ぐきが少し赤くなっているが出血はほとんどない
これらは、軽い歯ぐきの炎症や刺激による一時的な反応です。
ただし、1週間以上続いたり、痛みが強くなる場合は、虫歯や歯周病が隠れていることもあるため、軽い症状でも長引くときは、早めに歯科医院で確認してもらうことが大切です。
受診が遅れたときのリスク
痛みを我慢して放置すると、症状が進行し、治療の負担や費用が大きくなります。
初期の虫歯なら小さな詰め物で済みますが、神経まで達すると根管治療が必要になり、通院回数や治療にかかる費用の負担は避けられません。
さらに、歯ぐきの炎症を放置すれば歯を支える骨が溶け、最終的に抜歯が必要になることもあります。
炎症が広がると顔が腫れ、顎の骨や全身にまで影響を及ぼすこともあります。
特に発熱や強い腫れを伴う場合は、早急に歯科医院を受診することが大切です。
関連記事:歯が痛い すぐに歯医者に行けない人のための応急ケアと受診目安6選
再発を防ぐための3つの歯間ケアのコツ

痛みがいったん治まっても、しばらくすると同じ場所がまた痛むことがあります。こうした再発を防ぐには、毎日の歯間ケアを正しく行うことが大切です。
以下では、歯と歯の間の痛みを繰り返さないための3つのポイントを解説します。日々のケアを少し工夫するだけで、再発のリスクを大きく減らすことができるでしょう。
歯間ブラシ・フロスの正しい使い方
再発を防ぐための基本は、歯と歯の間に汚れをためないことです。
歯間ブラシは、隙間の大きさに合ったサイズを選ぶことが大切です。大きすぎると歯ぐきを傷つけ、小さすぎると汚れが残ります。毛先を軽く前後に動かし、無理に押し込まないようにしましょう。
デンタルフロスを使う場合は、歯の側面に沿わせて上下に動かし、面をなぞるように汚れを落とします。強くこすらず、滑らかに通すのがコツです。
歯間ケアは1日1回、就寝前に行うのが理想的です。夜は唾液の分泌が減り、細菌が繁殖しやすくなるため、寝る前のケアを習慣にしておくとよいでしょう。
強く磨かない!歯ぐきを守るブラッシング方法
歯をきれいにしようと強く磨いてしまう人は少なくありません。
しかし、力を入れすぎると歯ぐきが傷つき、炎症を悪化させる原因になります。
歯ブラシはペンを持つように軽く握り、毛先を歯と歯ぐきの境目に45度の角度で当て、細かく優しく動かすのが基本です。
硬い毛のブラシよりも、やわらかめのブラシを選べば、出血や摩耗を防げます。
また、歯みがき粉の使いすぎにも注意が必要です。研磨剤が多く含まれるタイプは歯の表面を削ることがあるため、「低研磨」や「フッ素配合」と表示されたものを選ぶとよいでしょう。
定期検診とクリーニングの大切さ
自宅でのケアに加えて、定期的に歯科医院でプロによるクリーニングを受けることが、再発を防ぐ大切なポイントです。
歯科医院では、歯ブラシでは届かない深い部分の汚れ(歯石やバイオフィルム)を専用の機器で除去します。
さらに、歯ぐきの状態や噛み合わせ、初期の虫歯などもチェックできるため、トラブルを早期に発見できます。
一般的には3〜6か月に1回の定期検診が理想的です。痛みがなくても「予防のために通う」という意識を持つことが、歯を長く保ついちばんの近道です。
まとめ|早めの受診で大切な歯を守ろう
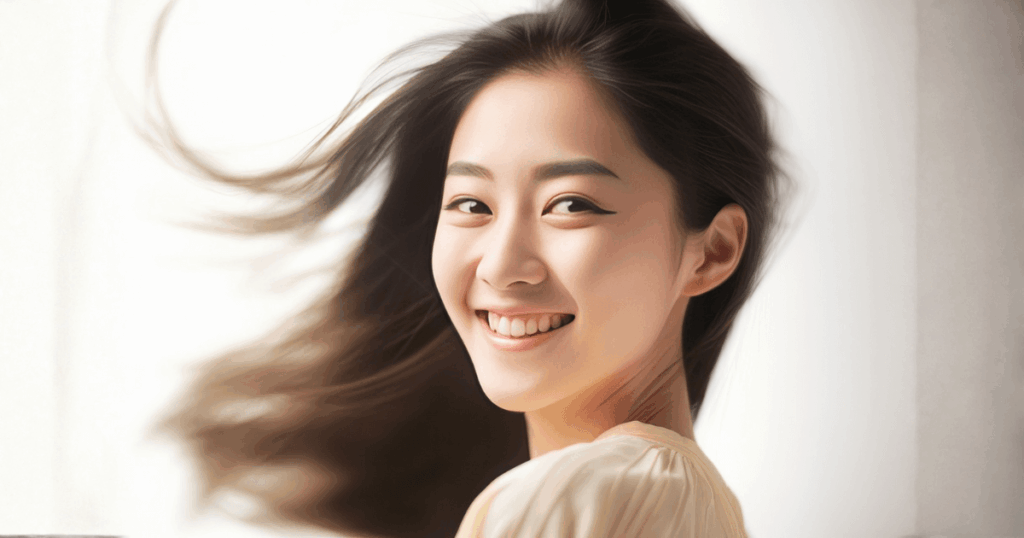
歯と歯の間の痛みは、食べ物のつまりや軽い炎症など一時的なものから、虫歯や歯周病、神経の炎症など治療が必要なケースまで、原因はさまざまです。
初期のうちは我慢できる程度でも、放置すると炎症が広がり、治療が長引いたり、歯を失う結果につながります。
まずは自宅で正しいケアを続けながら、痛みが長く続く場合や気になる症状がある場合は、できるだけ早めに歯科医院を受診しましょう。
早期に原因を見つけて治療を行えば、神経を残せる可能性が高まります。
毎日の歯間ケアと定期的な検診を習慣にして、痛みの再発を防ぎながら、健康な歯を長く保ちましょう。
愛知県半田市で歯医者をお探しなら「歯科ハミール本院」
名鉄「住吉町駅」より徒歩1分の歯医者
当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。
この記事を監修した人

歯科ハミール本院 院長 赤崎 絢
所属学会
略歴