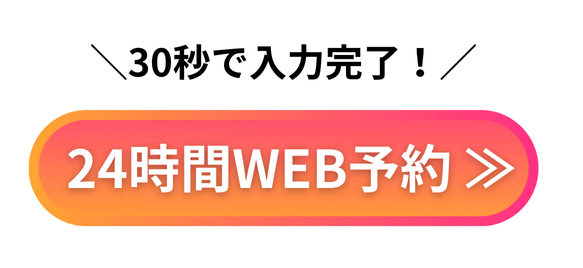「抜歯したあと、歯を入れるまでどのくらいかかるの?」「仮歯の期間はどう過ごせばよいのかな……」
そんな疑問や不安を抱く方は少なくありません。
抜歯後は、歯ぐきや骨の回復具合によって治療を始める時期が異なるため、治療期間には個人差があります。
回復の仕組みを理解しておけば、不安を和らげながら落ち着いて治療を進められるでしょう。
この記事では、抜歯後から歯を入れるまでの一般的な流れと期間の目安をはじめ、入れ歯・ブリッジ・インプラントといった治療法の違いを整理します。
さらに、仮歯で快適に過ごすための工夫や注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
抜歯後に歯を入れるまでの流れと期間の3つのポイント
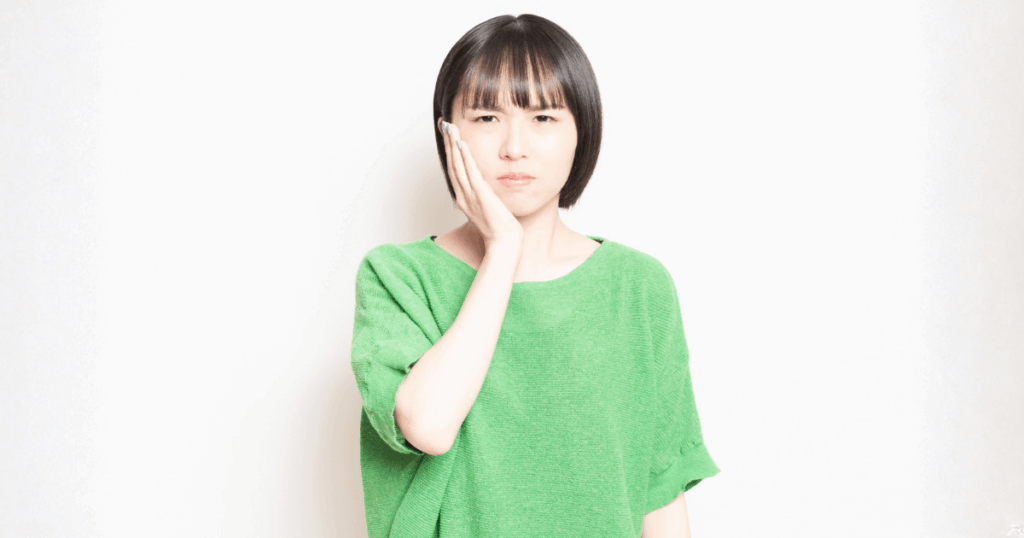
抜歯を終えたあと、歯を入れられるまでの期間は気になるものです。
治り方には個人差がありますが、歯ぐきの傷がふさがり、内部の骨が安定するまでにはある程度の時間が必要です。
一般的な治療の流れは三段階です。はじめに抜歯後の傷が治り、続いて骨の再生が進み、最後に歯を入れる準備が整います。
それぞれの段階について詳しく見ていきましょう。
抜歯直後から治癒までにかかる期間
抜歯をした直後は、傷口がまだ不安定な状態です。
数日かけて血液が固まり(血餅:けっぺい)、その膜が傷を守りながら少しずつ歯ぐきが再生していきます。
1〜2週間ほど経つと表面が落ち着き、見た目には治ったように見えるでしょう。ただし、内部では骨の修復が進行中です。
骨がしっかりと再生するまでには2〜3か月ほどかかるのが一般的で、外見よりも治癒のペースはゆるやかです。
この時期に強いうがいや硬い食べ物をとると、血餅が剥がれて治りが遅れることがあります。
歯科医院では、傷口の状態を確認しながら、仮歯の装着や本格的な治療へ移るタイミングを慎重に判断します。
歯ぐきと骨の回復スピードの違い
歯ぐきと骨では、回復にかかる期間が異なります。
歯ぐきの柔らかい組織は再生が早く、抜歯後1〜2週間ほどで表面が閉じて安定します。
一方で、内部の骨は時間をかけてゆっくりと再生し、完全に固まるまでには4〜6か月ほど必要です。
この骨の再生は、抜歯した部分を支えるために欠かせない過程です。
骨の回復が十分でないうちに治療を進めると、インプラントが安定しなかったり、将来的にぐらつきの原因になったりします。
そのため、歯科医院ではレントゲンなどで骨の状態を確認しながら、治療のタイミングを慎重に見極めます。
実際に歯を入れられるのはいつから?
抜歯から歯を入れるまでの期間は、一般的に3〜6か月が目安です。ただし、歯ぐきや骨の回復速度には個人差があり、治療方法によってもタイミングは異なります。
抜歯後すぐに仮歯を入れる即時義歯を選べば、見た目の空白を避けながら治療を進められます。
一方で、炎症が残っていたり骨の再生が遅れていたりする場合は、半年以上かかることもあります。
治療を急がず、定期的に状態を確認しながら進めることが大切です。
歯科医院では、歯ぐきや骨の回復具合を診察し、仮歯から本格的な歯へ移行する最適なタイミングを判断します。
見た目や噛み合わせを整えながら治療を進めるためにも、医師の指示に従い段階的に治療を行いましょう。
関連記事:抜歯しないといけない歯を放置したら…10年後の怖いリスク
抜歯後の治療方法を比較する3つの選択肢と選ぶポイント

歯を抜いたあとの治療には、いくつかの選択肢があります。見た目の自然さや費用、治療期間など、重視する点によって最適な方法は異なります。
それぞれの特徴を理解しておけば、自分に合った治療を選びやすくなるでしょう。
主な治療法は、入れ歯・ブリッジ・インプラントの三つです。
ここでは、それぞれの特徴と選ぶ際のポイントを詳しく紹介します。
入れ歯|費用を抑えて早く入れられる方法
入れ歯は、抜歯後の治療のなかでもっとも一般的な方法です。歯ぐきの回復を確認してから型取りを行い、早ければ2〜4週間ほどで装着できます。
保険が適用される場合は、1〜3万円程度で作製できることが多く、費用を抑えたい方に向いています。
見た目や咬み心地を重視する場合は、自由診療による精密義歯を選ぶことも可能です。
ただし、取り外しの手間や装着時の違和感を感じやすい点はデメリットでしょう。
また、時間の経過とともに口の形が変わるため、定期的な調整や作り直しが必要になることがあります。
ブリッジ|周囲の歯を支えにする固定式の治療
ブリッジは、失った歯の両隣にある健康な歯を削って土台を作り、その上に人工の歯を橋のように固定する治療法です。
見た目が自然で、装着後の違和感が少ない点が特徴です。入れ歯のように取り外す必要がなく、噛む力も安定しています。
一方で、健康な歯を削るため、将来的に歯への負担がかかりやすいのが注意点です。
治療期間はおよそ2〜3週間で、保険が適用される場合は1本あたり2〜5万円程度が目安です。
見た目の自然さと治療の早さを両立できる方法として、多くの症例で選ばれています。
インプラント|自然な見た目と噛む力を再現できる方法
インプラントは、人工の歯根をあごの骨に埋め込み、その上に人工歯を装着する治療法です。
見た目や噛む力の再現性が高く、天然の歯に近い感覚を取り戻せるのが特徴です。
外科的な処置を伴うため、治療期間は3〜6か月と比較的長く、費用も1本あたり30〜50万円(税込)が目安です(自由診療)。
骨の量が足りない場合は、骨を補う骨造成(GBR)を行うこともあり、その分期間が延びるケースもあります。
インプラントは耐久性に優れており、定期的にメンテナンスを行えば、10年以上にわたって使用できることも多く報告されています。
自分に合う治療法を選ぶポイント
治療法を選ぶ際は、費用・見た目・耐久性・メンテナンスのしやすさという四つの観点から考えることが大切です。
どの要素を優先するかによって、選ぶべき方法が変わります。
短期間で治療を終えたい場合や費用を抑えたい場合は、入れ歯が向いています。
長期的な安定性や自然な噛み心地を重視するなら、インプラントを検討するとよいでしょう。
ブリッジはその中間に位置し、見た目と機能のバランスを取りたい方に適しています。
また、歯ぐきや骨の状態、持病の有無によって適した治療は異なります。
カウンセリングの際には、複数の治療法を比較しながら、自分の生活や希望に合う方法を医師と一緒に検討しましょう。
| 治療法 | 期間の目安 | 費用の目安 | 主な特徴 |
| 入れ歯 | 2〜4週間 | 1〜3万円(保険適用) | 費用が安く、早く作れるが違和感がある |
| ブリッジ | 2〜3週間 | 2〜5万円(保険適用) | 見た目が自然だが健康な歯を削る必要あり |
| インプラント | 3〜6か月 | 30〜50万円(自由診療) | 見た目・噛む力ともに天然歯に近い |
関連記事:インプラント手術の前に知っておきたい5つの重要なポイント
歯がない期間を快適に過ごすための3つの工夫

抜歯をしてから歯を入れるまでの間は、見た目や食事の不便さを感じやすい時期です。
しかし、この期間を少し工夫するだけで、快適に過ごしながら治療を進めることができます。
日常生活の負担を減らすための工夫を取り入れれば、治療への不安も和らぐでしょう。
ここでは、仮歯の活用法・即時義歯のメリット・食事や会話の注意点の三つを中心に解説します。
それぞれのポイントを順に見ていきましょう。
仮歯(暫定義歯)を使う目的と期間
仮歯は、抜歯後に歯ぐきや骨が安定するまでの間に装着する一時的な義歯です。
見た目を整えるだけでなく、隣の歯が動くのを防ぎ、噛み合わせのバランスを保つ役割も果たします。
装着期間は治療内容によって異なりますが、一般的には1〜3か月が目安です。
治療中でも自然な見た目を保てるため、仕事や人前に出る機会が多い方にも安心感があります。
ただし、固定力が弱く外れやすい場合があるほか、硬い食べ物を噛むときには注意が必要です。
定期的な調整を受ければ、違和感を減らし快適に使い続けやすくなります。
即時義歯で見た目の空白を防ぐ方法
抜歯後の見た目が気になる方には、即時義歯(そくじぎし)という方法があります。
これは、あらかじめ抜歯前に型を取っておき、当日に義歯を装着する治療法です。
歯を失った直後から歯が入った状態を保てるため、見た目の空白期間をつくらずに過ごせます。
また、抜歯直後の傷口を保護する役割もあり、出血や痛みを軽減できるのがメリットです。
ただし、歯ぐきが回復するにつれて形が変化するため、時間の経過とともに義歯が合わなくなります。
再調整や作り直しを行えば使い続けられるでしょう。
食事や会話で気をつけたいこと
抜歯後の回復期間は、噛む力が弱まりやすく、食事や会話に影響が出ます。
特に最初の1〜2週間は、やわらかい食事を中心にして、強く噛む動作を避けるようにしましょう。
硬い肉やせんべい、粘着性のあるお餅やガムなどは、傷口を刺激しやすいため控えるのが安心です。
この時期に刺激を抑え、無理のない範囲で栄養を取ることが回復を早めます。
一方で、片側だけで噛むなど偏った使い方をすると、噛み合わせのバランスが崩れる可能性があります。
仮歯や義歯を使用している場合は、定期的に歯科医院で調整を受けながら、正しい噛み方を保つようにしましょう。
関連記事:親知らず抜歯後にやってはいけないこと7選|抜歯後におすすめの食事も紹介
抜歯後に放置すると起こる3つのリスクと注意点

抜歯後、痛みがなくなると「もう治った」と感じてしまう方も少なくありません。
しかし歯を入れずにそのまま放置すると、見た目の変化だけでなく、噛み合わせや身体全体のバランスにも影響を及ぼします。
放置期間が長くなるほど、後の治療が複雑になりやすいため注意が必要です。
ここでは、抜歯後に起こりやすい3つのリスクとして、骨が減る理由・骨を守るための処置・放置による治療への影響を解説します。
早めに対処すれば、将来のトラブルを防げるでしょう。
抜歯後に骨が減る理由
歯を抜いたあとは、歯を支えていた骨(歯槽骨)が役割を失うため、徐々に吸収されていきます。
この骨吸収は体の自然な反応であり、特別な異常ではありません。
ただし、放置すると数か月のうちに骨の高さや厚みが大きく減少する場合があります。
抜歯から半年ほどで骨の幅が30〜40%ほど狭くなるケースも報告されており、注意が必要です。
骨が減少すると、将来的にインプラントやブリッジを支える土台が弱くなり、治療が難しくなるおそれがあります。
そのため、抜歯直後から骨を守るケアを行うことが大切です。
骨を守るための処置(ソケットプリザベーションなど)
抜歯後の骨吸収を抑える方法として、ソケットプリザベーション(骨保存療法)があります。
これは、抜歯後に残った穴(ソケット)へ骨補填材を入れ、骨が痩せるのを防ぐ処置です。
将来的にインプラント治療を希望する場合にも、骨の土台を維持するために役立ちます。
この処置は抜歯と同時に行われることが多く、痛みはほとんどありません。
骨の高さや厚みを保ちやすくなるほか、歯ぐきの形を維持しやすいという見た目の利点もあります。
ただし、感染や炎症がある部位では適用できないため、すべての症例に行われるわけではありません。
インプラントを検討している場合は、抜歯前の段階でその意向を医師に伝えておくと、治療計画がスムーズに進みます。
放置による治療への影響
歯を入れずに長期間放置すると、周囲の歯が抜けた部分に傾いたり、噛み合わせが乱れたりします。
この状態になると、ブリッジを作る際に土台の位置がずれてしまい、正しく装着できません。
さらに、噛む力のバランスが崩れることで顎関節に負担がかかり、肩こりや頭痛などの症状を引き起こします。
また、上の歯が下に伸びてくる挺出(ていしゅつ)が起こると、見た目の変化にもつながります。
こうしたトラブルを防ぐには、抜歯後できるだけ早く仮歯や義歯を入れてスペースを保つことが大切です。
早期に対応することで、後の治療をよりスムーズに進められます。
関連記事:虫歯のなりかけを放置するとどうなる?治療費と痛みを防ぐ対策4つ
治療をスムーズに進めるための3つのポイント

抜歯後の治療を安心して進めるためには、事前の準備と通院中の工夫が欠かせません。
少しの意識と行動で、治療期間を短縮したりトラブルを防いだりすることができます。
ここでは、治療前に確認しておきたいこと・通院中に相談したいポイント・安心して治療を受けるための心構えの三つに分けて紹介します。
治療前に確認しておきたいこと
治療を始める前は、「どの治療法を選ぶか」だけでなく、「治療後にどのような生活を送りたいか」を考えておくことが大切です。
仕事や食事のスタイル、見た目の希望によって、適切な方法は人それぞれ異なります。
また、持病や服薬している薬の内容によっては、治療に制限が出ることもあります。安全に進めるためにも、あらかじめ医師へ正確に伝えておきましょう。
さらに、歯ぐきや骨の状態によって治療期間は大きく変わります。見積もり段階で、通院回数やおおよその治療期間を確認しておくと安心です。
費用やメンテナンスの内容も含め、後から想定外の負担が生じないよう事前に整理しておくことが重要です。
通院中に医師へ相談したいポイント
治療を進める途中で、仮歯の違和感や痛みを感じたときは、我慢せず早めに相談しましょう。噛み合わせが合わないときも同様です。
小さな不具合を放置すると、炎症や歯ぐきの変形につながり、結果的に治療期間が延びるおそれがあります。
また、治療方法を変更したいと感じた場合も、ためらわずに意思を伝えることが大切です。
歯科医師は患者の希望に合わせて治療計画を調整できるため、遠慮する必要はありません。
さらに、仮歯や義歯を装着したあとに噛み合わせの感覚が変わることもあります。
食事中に浮く、片側でしか噛めないなどわずかな違和感でも共有しておくと、早期に調整が行いやすくなります。
不安なく治療を受けるための心構え
抜歯後の治療は、数か月に及ぶこともあるため、焦らず着実に進める姿勢が大切です。
特にインプラントのように、骨の再生を待つ治療では「なかなか終わらない」と感じることもあるでしょう。
しかし、治癒の進行を見極めながら慎重に進めるからこそ、長期的に安定した結果につながります。
また、治療期間中は生活習慣の見直しも欠かせません。
喫煙や睡眠不足は治癒を遅らせる要因になるため、できる範囲で生活習慣を整えましょう。
治療は医師任せではなく、自分も回復に前向きに取り組む意識を持つことが、スムーズな完治へつながります。
まとめ|抜歯後の治療期間を知って、納得の治療を進めよう

抜歯後に歯を入れるまでの期間は、歯ぐきや骨の回復状態によって異なります。一般的には3〜6か月が目安ですが、治療法や体質によって前後する場合もあります。
早く歯を入れたい場合でも、無理に進めるとトラブルの原因になります。医師の判断に従いながら、適切なタイミングを見極めることが大切です。
入れ歯・ブリッジ・インプラントにはそれぞれ特徴があり、希望や生活スタイルに合った方法を選ぶことで、長く快適な状態を保てます。
また、仮歯や即時義歯を活用すれば、見た目や生活の不便さを軽減することも可能です。
放置による骨の減少や噛み合わせのズレを防ぐためにも、早めの相談と定期的なケアを心がけましょう。
焦らず、自分のペースで治療を続けていけば、満足のいく結果につながります。
愛知県半田市で歯医者をお探しなら「歯科ハミール本院」
名鉄「住吉町駅」より徒歩1分の歯医者
当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。
この記事を監修した人

歯科ハミール本院 院長 赤崎 絢
所属学会
略歴